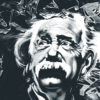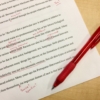秋からでも間に合う!受験勉強の追い込み計画で逆転合格を狙う方法
夏が終わり、空気が冷たくなってくる秋。
この季節は、多くの受験生にとって“勝負の分かれ道”です。
夏に思うように結果が出なかった人も、ここからの行動次第で大きく流れを変えることができます。
「秋からじゃ遅いのでは…」と思っていませんか?
実は、秋以降に一気に伸びて逆転合格する生徒は、毎年少なくありません。
それは、ここからの数ヶ月を“正しく計画して実行できた人”だけが手にできる結果です。
勉強時間を増やすだけではなく、どこに時間をかけ、どうやって得点を伸ばすか。
この“戦略の立て方”が、あなたの未来を決めます。
本ブログでは、長期戦略・目標設定からの逆算型プランが多く紹介されていますが、それは “余裕ある人向け” の面もあります。
この記事では、それよりもさらに「やるべきことを絞り、無駄を省き、最後まで持たせる力を設計する」ことを重視した「直前仕様・追い込み型プラン」を提案します。
目標はただ「勉強量を増やす」ことではなく、「入試本番で点を取る力・勝負できる体力を残す」ための設計です。
秋からの勉強に必要なのは「絞る勇気」
まず意識してほしいのは、「全部やろう」と思わないこと。
秋以降は時間が限られているため、広く浅くよりも、狭く深くの方が得点に直結します。
最初にすべきは、現状の正確な分析です。
最近の模試や過去問演習を見返し、「点が取れていない原因」を分野ごとに洗い出しましょう。
たとえば、数学なら「ベクトル」「数列」、英語なら「長文読解」「文法整序」など、具体的に挙げてください。
その上で、
・出題頻度が高い
・伸びしろが大きい
・配点が高い
この3つに該当する分野を最優先にします。
秋の勉強は「弱点克服の総仕上げ」ではなく、
“入試で落とせない部分を確実に得点源に変える”段階です。
11月:基礎の穴埋め+型づくり期
夏の学習で知識は増えたものの、「正確さ」と「スピード」が伴っていない人が多い時期です。
ここでは、得点の安定感をつくるための基礎固めを行います。
やるべきことは3つ。
①「弱点分野リスト」をつくる。
模試や過去問を見て、正答率が低かった単元をすべて書き出します。
「なんとなく苦手」ではなく、問題番号・テーマ単位で具体的に。
② 優先順位をつけて潰す。
全てを克服するのは難しい。
残り時間で“点数が上がる”部分を中心に取り組みましょう。
例えば、英語なら「長文の精読・設問処理」、数学なら「典型問題の処理スピード」など。
③ 毎週チェックする。
週に一度、自分の勉強記録を振り返り、「今週できるようになったこと/まだできないこと」を整理します。
この習慣がある人とない人では、11月以降の伸びがまったく違ってきます。
11月:模試と実戦演習を中心にする
この時期から、模試や過去問演習を“本番訓練”として扱います。
単なる力試しではなく、「試験時間内で得点する力」を磨く段階です。
模試を受けたら、必ず次の3ステップを徹底してください。
1.解説を読み、なぜ間違えたのかを言語化する。
2.類題を探して翌週中にもう一度解く。
3.ミスノートにまとめ、同じミスを繰り返さない。
模試は結果を見て一喜一憂するものではなく、自分の課題発見装置です。
結果の数字よりも、「何を直せば上がるのか」に注目しましょう。
この頃から、共通テスト形式の問題にも慣れていく必要があります。
英語リーディングや国語などは形式慣れが点数を大きく左右します。
時間を計って解く練習を始め、制限時間内に全問に触れるリズムを掴んでください。
12月:共通テスト対策に全振り
12月は、共通テスト対策に集中する時期です。
年末にかけては、「過去問」「予想問題」「模試演習」を繰り返し、実戦力と安定感をつくります。
過去問は最低3年分、できれば5年分解いてください。
大切なのは「解く→直す→もう一度解く」というサイクル。
一度間違えた問題を放置するのは、時間の浪費です。
同じミスを繰り返さないことが、最も効率の良い得点アップ法です。
また、各科目で「自分が落としがちなパターン」を書き出しましょう。
例えば、
英語:文法ケアレスミス
数学:計算順序の混乱
化学:単位換算ミス
といった“自分専用のミスリスト”をつくっておくと、本番前に確認できます。
年末にかけては疲れが溜まりやすくなります。
一気に詰め込みすぎず、1日おきに“軽めの日”を作るのも戦略です。
睡眠不足や体調不良は、どんな勉強よりも点数を下げる要因になります。
1月:実戦演習+最終補正期
年が明けたら、残りはもうラストスパート。
この時期は“実戦モード”で週ごとに模試・演習を繰り返します。
ただし、回数を増やすだけでは意味がありません。
模試と模試の間に、必ず「復習・調整日」を入れましょう。
演習のたびに、自分の得意・不得意がはっきり見えてきます。
そこで次のように、毎日の学習を3つに分けてみてください。
・得意科目:安定感を保つための維持練習
・不安科目:弱点克服のための短時間集中演習
・共通科目:共通テスト形式で時間感覚を保つ演習
模試で点が伸びなくても焦らないでください。
この時期の模試は「調整の場」です。
本番直前のコンディションを整えるつもりで取り組みましょう。
試験直前期:整えることに徹する
試験の直前になったら、新しいことに手を出すのはやめましょう。
ここからは「確認」と「体調維持」がすべてです。
毎日、各科目で「これだけは見直しておきたい基本事項」をリストにまとめて、軽く回します。
朝の英単語復習、昼の公式確認、夜の小テストなど、短時間でできる復習をルーティン化するのが理想です。
また、本番の時間割に合わせたシミュレーションを1〜2回やっておくと、本番当日の緊張を軽減できます。
起床時間・朝食・試験開始時刻まで、できるだけ本番通りに過ごしてみてください。
無理に夜遅くまで勉強せず、身体と心を休めることが、最後の勝負を左右します。
「追い込み型計画」で意識すべき5つの鉄則
1.優先順位をつける勇気を持つ。
全部を完璧にしようとせず、「合格に必要な部分」に絞る。
2.模試を“練習”ではなく“本番シミュレーション”として使う。
本番の流れ・時間・集中の持続を、模試で訓練する意識を。
3.復習こそが最大の伸びしろ。
解きっぱなしをなくし、「なぜ間違えたか」を掘り下げること。
4.体調・メンタル管理を“勉強の一部”と考える。
睡眠・休憩・食事のリズムを固定化して、本番も同じ調子を保つ。
5.焦らず、諦めず、最後までルーティンを守る。
伸びる人は「最後までやりきった人」。途中で迷って計画を崩さないことが大切です。
まとめ:秋の頑張りが「奇跡」を生む
秋からの数ヶ月は、決して“遅すぎる”わけではありません。
この時期に「どこまで集中できるか」「何を削ぎ落とせるか」で結果は大きく変わります。
周りと比べず、昨日の自分を超えることだけを意識して進んでください。
今日から始めるあなたの追い込みが、きっと本番での一問を変え、志望校合格へと繋がります。
詳しくはYouTubeチャンネル「教育嬢TV」でもお話ししています。ぜひご覧ください🙇♀️

受験メンタルトレーナー/チャイルドコーチングアドバイザー/JAPAN MENSA会員
地方公立中高一貫校から特色入試(AO入試)で京都大学薬学部に現役合格
中高時代は運動部の活動・個人研究・学業を両立
大学在学中は大手予備校の塾講師として勤務し、受験指導やメンタルサポートの経験を積む
卒業後は母校でアドバイザーとして高校生の指導、地元個人塾でカリキュラム作成、オンラインを中心とした受験コンサルティングも展開中