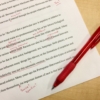【完全保存版】秋から本番までの受験勉強ロードマップ!共通テスト&二次試験の戦い方
大学受験は長いマラソンのようなものですが、夏休みを終えるといよいよ本番までのラストスパートに入ります。秋から冬にかけての勉強の仕方次第で、共通テスト、そして2次試験に臨む自信が大きく変わってきます。ここでは、秋から大学受験本番までの流れを時期ごとに整理し、勉強のポイントを具体的にまとめました。
2026年1月17日(土)18日(日)の共通テスト、そして2月25日(水)からの国公立大学前期試験に向けて、いつ何をするべきか、いつから過去問を解くべきか、お話しししていきます。
9月〜10月:土台固めと仕上げの演習
夏休みの勉強で一通りの範囲を学習し終えた人もいれば、まだ手をつけ切れていない問題集が残っている人もいるはずです。9月と10月は「残った課題を片付ける時期」と考えると分かりやすいでしょう。
夏に取り組んだ問題集を未完成のまま放置すると、秋以降の過去問演習の効果が半減してしまいます。ですから、この時期は 夏にやり切れなかった問題集をしっかり最後までやり切ること が重要です。
また、過去問演習に入る前の準備として、1冊演習問題集を挟むのも効果的です。私は化学において、夏休み中に『重要問題集』と『有機化学演習』を終わらせ、過去問演習の前に『化学の新演習』からピックアップした問題を解き進めました。こうすることで、基礎から応用までの流れがスムーズにつながり、過去問演習に入ったときに得点力を実感できるようになりました。
10月〜11月:2次試験過去問と弱点補強
秋が深まってきたら、いよいよ 2次試験の過去問演習 に取り組む時期です。ここで大切なのは「ただ解くだけで終わらない」ということ。過去問を解いてみると、自分の抜けや弱点が必ず見えてきます。
過去問を解いたら必ず復習をして、弱点を1つずつ潰していく。この「過去問→復習→補強」のサイクルを何度も繰り返すことが、2次試験での安定した得点につながります。
12月:共通テスト特化演習
共通テスト本番は2026年1月17日(土)・18日(日)に行われます。そこから逆算すると、12月は共通テスト特化の勉強に切り替えるのが一般的です。
学校でも共通テスト演習が始まる時期なので、授業内での対策は学校に任せて、放課後や自宅学習では引き続き2次試験対策を進めるというスタイルも可能です。ただし、理系科目や国語など「本番の形式に慣れる必要がある科目」は自習でもしっかり練習する必要があります。
共通テストの過去問は本試験・追試験を合わせて10回分あります。クリスマス頃から取り組み始めても、2日で1年分のペースでもちょうど20日間で解き終えることができます。焦る必要はありませんが、12月のうちに少しずつ取り組んでおくと安心感が増します。
この期間に注意してほしいのは、数学だけはマークと記述対策の両立を続けるということです。
誘導のあるマーク数学と問題文の短い記述数学では頭の使う部分が違うため、どちらかの対策に偏ってしまうと、感覚を忘れてしまうことがあります。
1月:共通テスト直前〜本番
いよいよ受験生全員が意識する共通テスト本番。直前の1月上旬は、これまで解いた過去問の復習を中心に、ケアレスミスを減らす練習や時間配分の確認を行いましょう。
本番当日は、焦らず普段の演習通りの感覚で解くことが大切です。特に時間との戦いになるため、難しい問題に固執せず、取れる問題を確実に取る姿勢を持ちましょう。
共通テスト〜3日後:自己採点と出願校決定
共通テストが終わったら、まずは自己採点です。
大学によっては共通テストの点数によって出願校を決める必要があるため、受験生にとって非常に大事な期間になります。
出願校の決定は、共通テストの結果と2次試験への自信の両方を踏まえて行うことが必要です。ここで無理に背伸びをするよりも、自分の力を最大限に発揮できる大学を選ぶことが合格につながります。
1月下旬〜2月:私立大学入試と前期試験対策
共通テストが終わると、前期試験までは残り5週間ほど。この間に私立大学入試と国公立前期試験の対策を進めます。
私立大学を併願する人は、過去問を1〜3年分解いて傾向を把握し、知識チェックを兼ねる程度で大丈夫です。併願校に力を入れすぎて前期試験の対策が不十分になってしまっては本末転倒。あくまで「前期試験が本命」という姿勢を崩さないようにしましょう。
一方で「前期試験一本で勝負する」という受験生は、私立大学を受けず、この5週間をすべて前期試験の過去問演習に費やす場合もあります。志望校に全力を注ぎたいタイプの人には、このやり方も有効です。
2月下旬:前期試験本番
2026年2月25日(水)から国公立大学前期試験が始まります。共通テストから約1か月以上あったとしても、あっという間に本番がやってきます。ここまでに積み重ねてきた演習と弱点克服が、そのまま実力として試される場面です。
緊張するのは当然ですが、これまでの努力を信じて試験に臨みましょう。
後期試験について
「後期試験の対策も今からやっておかないと…」と不安に思う人もいるかもしれません。しかし後期試験は前期試験に比べて科目数が少なく、小論文や面接中心の大学も多いです。そのため、後期試験の準備は前期試験が終わってからでも十分間に合います。まずは前期試験に全力を尽くすことが最優先です。
まとめ
秋から受験本番までの流れを振り返ると、次のようになります。
9月〜10月:夏にやり切れなかった問題集を完成させる。演習問題集を挟んで過去問に入る準備。
10月〜11月:2次試験の過去問演習。解いて弱点を見つけ、補強を繰り返す。
12月:共通テスト特化。過去問10回分を20日程度で取り組む。
1月:共通テスト本番。直前は復習と時間配分の確認。
1月下旬〜2月:私立入試と前期試験対策。併願は必要最小限に。
2月25日以降:前期試験本番。後期は前期終了後で間に合う。
受験は長期戦ですが、秋からの流れを正しく理解し、自分に合った勉強法を選ぶことで、着実に合格へ近づくことができます。皆さんが自分の努力を信じて、最後まで走り抜けられることを願っています。
詳しくはYouTubeチャンネル「教育嬢TV」でもお話ししています。ぜひご覧ください🙇♀️

受験メンタルトレーナー/チャイルドコーチングアドバイザー/JAPAN MENSA会員
地方公立中高一貫校から特色入試(AO入試)で京都大学薬学部に現役合格
中高時代は運動部の活動・個人研究・学業を両立
大学在学中は大手予備校の塾講師として勤務し、受験指導やメンタルサポートの経験を積む
卒業後は母校でアドバイザーとして高校生の指導、地元個人塾でカリキュラム作成、オンラインを中心とした受験コンサルティングも展開中