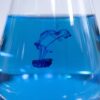京大薬学部卒がおすすめする共通テスト国語の参考書
今回は参考書紹介シリーズ第5弾として、共通テスト国語におすすめの参考書を紹介していきます。
私は理系ですが、2次試験で国語が必要だったため、しっかりと対策していました。とはいえ、2次試験対策は大学ごとの過去問を解いて先生に添削してもらうスタイルが中心だったので、新たに参考書を買い足すことはあまりありませんでした。それでも、高校生活で実際に使っていた参考書は、共通テストにも2次試験にも非常に役立ちました。
この記事では、文系・理系問わず、共通テストだけを受ける人にも、2次試験まで受ける人にもおすすめできる、国語の参考書を紹介していきます。
他教科の参考書については過去のブログ記事で紹介しています。気になる方はぜひご覧ください!
今回は現代文・古文・漢文の順に、基礎知識の定着におすすめ参考書を紹介したあと、最後には、どの分野にも共通して使える実戦的な問題集もあわせてご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
現代文
日本語である国語は、ものごころのついた時から触れているものなので、改めて勉強をしようと思うと何からすれば良いか分からないと感じてしまう人も多いはずです。
現代文の授業では覚えなければならない知識を新たに習うことも少ないので、勉強はどうしても後回しになってしまう人も多いかもしれません。
まずは語彙力を固める
現代文と聞くと、何となく“感覚で読む”というイメージがあるかもしれませんが、私は国語が苦手で、感覚に頼る読解はできないタイプでした。
だからこそ、まず語彙力をつけることから始めました。
使っていたのは、学校で配られた『現代文単語』です。
受験にやる気が出てきた高校2年生の夏からコツコツ読み進めました。
英語や古文には単語帳があるのに、現代文の単語は対策を忘れがち。
評論文などでは普段の生活では使わないような抽象的な言葉が頻出します。
特に共通テストでは、微妙な意味の違いを問う選択肢が多く、「どちらも合っている気がする…」と悩む人も多いのではないでしょうか?
そんなとき、選択肢の根拠を言語化できる語彙力がものを言います。
古文
次に古典は基礎的な知識が完璧になっていれば、国語が苦手な人でも、共通テストで満点を目指すことができる分野です。
「単語」「文法」「古文常識」の3点セットが揃えば、安定して点が取れるようになります。
私は以下のような流れで古文を強化しました。
・古文単語・文法(助動詞、敬語など)
・品詞分解を通して構造把握
・主語・敬語などを意識しながら読解
・演習問題で速読・大まかなあらすじをつかむ練習
古文単語
私が古文単語の勉強に使っていたのは、『マドンナ古文単語』。
この参考書は、300語以上を掲載する他の単語帳と違い、頻出の230語に厳選されており、重要な単語だけを効率よく覚えることができます。
特におすすめしたいのが、「文字量が少なくてイラスト付き」なところ。
私は暗記が苦手で、いかにも「勉強感」の強い単語帳はすぐに投げ出してしまっていた。
マドンナ古文単語は各単語の説明も文字は少なく、絵で表現されていて、眺めているだけでも自然と記憶に残るので、単語を覚えるのが苦手な人にも、古文に苦手意識がある人にもおすすめです。
古文常識
古文は現代語と文体も生活様式もまったく異なるので、背景知識がないと内容が頭に入ってきません。
現代文は今まで生きている中で背景知識がついていたり、身近なテーマも多く、文章中に分からない部分があっても知識で補って読むことができます。
それに比べて古文は非日常的な部分が多いので、1文ずつ読み進める中で理解できない文章に躓いてしまうと、情景が想像できないということもあります。
そこでおすすめなのが、『マドンナ古文常識』です。
学校では配布されなかったのですが、この1冊で古文で語られている時代の暮らしや文化を学べるため、慣れない形式の文章でも、情景が思い浮かび、流れがつかみやすくなりました。
物語の流れがつかめるようになるので、読解スピードも自然と上がってきます。
時間があるときに読み物としてパラパラめくるのもいいですし、読解中に分からないことがあれば辞書的に使うのもおすすめです。
漢文
漢文は古文よりも覚える知識量が少なく、形式もある程度パターン化されているので、どのようなテストでも得点源にしやすく、満点を目指せます。
漢文はまず句形・句法や語彙、訓読の基礎知識を身につけることが大切です。
その後、短文から文章読解へと進み、形式に慣れることで得点源にできます。過去問や問題集を活用した反復演習も効果的です。
私は、学校配布の『新明説漢文』という解説書を使っていました。
必要な句法や句形、語彙、訓読法、書き下しなどがコンパクトにまとまっており、辞書代わりに使える一冊です。
授業で分からなかった内容に付箋を貼って復習したり、模試前の総チェックに活用していました。
全科目共通の参考書
演習教材としては、
・『ゴロゴ』シリーズ(語呂で覚える)
・河合塾『マーク式基礎問題集 』
・駿台『短期攻略共通テスト』
・『共通テスト総合問題集』
・『黒本』
がおすすめです。
ゴロゴシリーズは基礎知識を楽しく身につけることができます。
河合塾と駿台の基礎問題集は基礎知識を身につけた後、過去問レベルの演習をする前に挟むのがおすすめです。
共通テスト対策
国語の実力を仕上げるためには、学校で配られる問題集を使用するのも良いですが、個人的には過去問を他の科目よりも多めに解くのがおすすめです。
私は、まず学校の授業内で共通テスト対策問題集を解き、次に本試験の過去問に取り組みました。
さらに力をつけたい人は、追試験の過去問にも挑戦してみましょう。
追試は本試験よりも難易度が高いと言われており、実際解いてみて難しく感じる問題もありました。
課題文が長かったり課題文自体が難しいというよりも、選択肢が難しい年もあって、ある程度力がついてから挑戦するとかなり練習になります。
私は1月に入ってから追試問題を解き始めたのですが、試験直前に実践力を鍛えるには最適な教材でした。
2次試験対策
最後に、2次試験でも国語が必要な方へ。
国語は点差がつきにくい科目ですが、安定して高得点を取るには「志望校の出題形式に似た大学の過去問」を解くのがコツです。出題傾向や文字数、問題構成が近いものを見つけて対策すると、実力を本番で発揮しやすくなります。
まとめ
国語は「なんとなく読めるけど点が取れない」と感じる人が多い科目ですが、語彙・文法・背景知識という“知識”をしっかり固め、演習で“慣れ”を作れば、確実に点数アップが狙えます。
ぜひ自分に合いそうな参考書から試してみてください!
詳しくはYouTubeチャンネル「教育嬢TV」でもお話ししています。ぜひご覧ください🙇♀️

受験メンタルトレーナー/チャイルドコーチングアドバイザー/JAPAN MENSA会員
地方公立中高一貫校から特色入試(AO入試)で京都大学薬学部に現役合格
中高時代は運動部の活動・個人研究・学業を両立
大学在学中は大手予備校の塾講師として勤務し、受験指導やメンタルサポートの経験を積む
卒業後は母校でアドバイザーとして高校生の指導、地元個人塾でカリキュラム作成、オンラインを中心とした受験コンサルティングも展開中
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/27b4ac14.ed904d0a.27b4ac15.7f9535fd/?me_id=1213310&item_id=21392595&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1469%2F9784342301469_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/27b4ac14.ed904d0a.27b4ac15.7f9535fd/?me_id=1213310&item_id=21149306&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7594%2F9784053057594_1_6.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/27b4ac14.ed904d0a.27b4ac15.7f9535fd/?me_id=1213310&item_id=21149339&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6665%2F9784053056665_1_6.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)