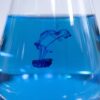大学受験合格に向けて!この夏使うべき、参考書まとめ
もうすぐ、夏休みに入ります。
夏休みはどのような勉強スタイルにするか、具体的にどの参考書を使うか、考えていますか?
夏休みは受験生にとって「天王山」とも言われるほど、大切な時期です。
私自身、この夏休みを有意義に過ごすことができ、一番成績が伸びたのは間違いなくこの時期でした。
計画を立てずに夏休みに突入してしまうと、大事な一ヶ月はあっという間に終わってしまいます。
せっかくの夏休み、無駄にしないためにも、早めに使用する参考書と勉強スケジュールを整理しておきましょう。
ということで、今回は理系と文系に分け、この夏休みにぜひ使ってほしい参考書を紹介します。
どの参考書も、私自身や実際に合格した友人たちが使っていたものばかりです。勉強を進める際の参考になれば嬉しいです。
理系
それではまず、理系におすすめの参考書を紹介します。
基礎に不安があるものは学校配布の基礎問題集、基礎が固まって自信のある科目は応用問題集に進むというのはどの科目にも共通しています。
国語
私は夏休みの毎朝、現代文単語とマドンナ古文単語230を決めたページ数で少しずつ覚えていました。
単語はただ読むだけでなく、青ペンで繰り返し書きながら覚えることを意識して取り組んでいました。
完全に暗記しようと力みすぎると続かなくなってしまうので、私は「とにかく毎日続ける」ということを大切にしました。
模試の前にはマドンナ古文常識や新明説漢文で古典常識と漢文の基本知識をざっと復習するようにして、知識が抜けていないかの確認を行いました。
夏までに、学校で配られていた錬成現代文・完成現代文・プログレス古典も進めていたので、演習がまだ足りないと感じている方は、学校の教材も上手に活用すると良いでしょう。
数学
選択がなく高校1年生から授業が進んでいることもあり、すでにかなりの進捗差がついているかもしれません。
夏休みはその差を埋める期間になります。
基礎がまだ不安だという方は、4STEPや4プロセス、プライムといった学校の定期テストレベルの問題集をしっかり固める。
ある程度基礎が固まってきた人は、青チャートやフォーカスゴールド、レジェンドのように、問題数が多く、かつ応用レベルに近い問題集にチャレンジすると効果的です。
さらに、難関大学を目指す人は、夏休みから大学への数学シリーズの新数学スタンダード演習やプラチカに進むのも良いでしょう。
ただし、自分の実力に合わない難問ばかりを解こうとせず、実力に合わせることが重要です。
私は実力が追いついていないのにも関わらず、夏休みに新数学スタンダード演習と京大25カ年に取り組み、数学に苦手意識を感じてしまった時期がありました。
英語
毎日、基礎固めとして、英単語の鉄壁を読み、英文法のヴィンテージには欠かさず取り組んでいました。
この習慣ができたおかげで、長文の構造が見えるようになり、得点にも繋がりました。
みなさんも、今取り組んでいる単語帳と文法問題集は、毎日少しずつでも触れ続けるのが良いでしょう。
応用としては、学校で配布されたWriting masterで英作文の練習をしたり、リスニング対策として「英語リスニングのお医者さん」にも取り組んでいました。
また、私はIELTs対策も兼ねていたため、英語4技能をバランスよく鍛えることを意識していました。
移動時間などの隙間時間には、システム英単語プレミアムの語源編を読み、知らない単語の意味を推測する力を養うことも続けていました。
気分転換にはTEDの英語プレゼンを聞き流し、耳を英語に慣らすことも習慣にしていました。
物理
私は名問の森を中心に取り組んでいました。
夏休みに入る前から解き始めていたので、夏休み中は間違えた問題だけを何度も解き直し、最終的に4周することができました。
名問の森と同じレベルで重要問題集もあります。
問題と解答が交互に繰り返される名問の森と解答が別冊になっている重要問題集、自分が使いやすい方を選ぶと良いでしょう。
演習をしている中で理解が曖昧だった単元は、センサー物理やセミナー物理、リードα物理といった基礎レベルの問題集に戻って確認するようにしていました。
物理の過去問は秋以降でも間に合うので、夏は焦らず、しっかりと基礎と応用問題を繰り返すことが重要です。
化学
有機化学演習と重要問題集(理論・無機・高分子)を徹底的に進めました。
私は夏の間にこの二冊を4周以上繰り返し、間違えた問題に何度も挑戦して、確実に身につけることを意識しました。
不安な単元があれば、セミナー化学などの基礎問題集に戻って基礎の確認をするのもおすすめです。
さらに、模試の前には鎌田の理論化学の講義など、全体をざっと整理できる読み物を使っていました。
余裕があり、さらに応用問題に挑戦したい方は、化学新演習にも夏から取り組むと秋以降がスムーズになります。
生物
学校で配られるセミナー生物などの問題集を繰り返し解いて、完璧になるまで仕上げることが大切です。
もし演習が足りないと感じた場合は、重要問題集などを購入し、一冊を徹底的に仕上げるのが良いでしょう。
大森徹の最強講義117講を辞書代わりに使い、わからない用語をその場で確認できるように手元に置いておくのもおすすめです。
地理
私は隙間時間を活用して、「地理Bの点数が面白いほどとれる本」を読んでいました。
考える勉強に疲れたときや、移動時間などに知識を積み重ねるのにぴったりの参考書です。
私は夏休み明けから過去問演習に入りましたが、理科科目が順調な人は夏から共通テストや模試の過去問に取り組んでも良いでしょう。
日本史
日本史は学校で配られている教科書や今までに受けた模試の解説を徹底的に読み込み、知識を増やしていくことが重要視される科目です。
定着した知識を確認するために、日本史B一問一答のような問題集を使うと効率良く知識の定着が図れます。
私が使っていた参考書は紹介した通りです。
高校3年生の夏は、特に理科に力を入れ、時間をかけていました。
文系
続いて文系のみなさんに向けた参考書は、東大など旧帝大文系学部合格者にご協力頂いてまとめました。
国語
文系の国語も基本的には理系と同様に、現代文単語とマドンナ古文単語230を使って基礎知識を固め、模試の前日にマドンナ古文常識と新明説漢文で知識を深めることがおすすめです。
演習としては、学校配布の錬成現代文・完成現代文・プログレス古典などの問題集に取り組み、演習が足りないと感じる方は、模試の過去問にも取り組むと良いでしょう。
記述演習のために、この時期から志望校の過去問や似た形式の問題に取り組み、先生に添削をお願いするとさらに力がつきます。
数学
数学は、共通テストで必要なレベルであれば、夏の間は4STEPや4プロセス、プライムなど、定期テストレベルの問題集をしっかり固めることをおすすめします。
記述試験でも必要な人は、夏休みの段階から模試の過去問などを活用し、実践的な演習を積むと良いでしょう。
英語
文系・理系どちらも学習スタイルは同じです。
私は毎日鉄壁とヴィンテージに取り組み、応用として学校配布のWriting masterや英語リスニングのお医者さんで英作文やリスニングの演習を行っていました。
文法書や単語帳は、少しずつでも毎日続けることが何よりも重要です。
世界史
山川出版社の詳説世界史を繰り返し読み込み、資料集としてタペストリーも活用するのがおすすめです。
他の教科書や資料集が配られている人はそちらを使用しても良いでしょう。
知識をインプットしたあとは、駿台の論述問題集やZ会の実力をつける世界史100題、一問一答を使うと、知識確認と論述力の強化に繋がります。
日本史
日本史も学校で配られている教科書や、今までに受けた模試の解説を徹底的に読み込み知識を増やしていくことが重要視される科目です。
知識確認のために日本史B一問一答、記述対策にはZ会の実力をつける日本史100題がおすすめです。
地理
「地理Bの点数が面白いほどとれる本」を読み進め、隙間時間を無駄にしないよう意識していました。
考える勉強に飽きたり、息抜きをしたいとき、気分転換にもなるので、負担なく続けられる一冊です。
理科基礎
理科基礎は、学校で配られている問題集、例えばリードαやセンサー、セミナーをひたすら繰り返すことで十分満点を目指せます。
さらに演習を重ねたい方は、模試の過去問を使用するとより実戦力が高まります。
夏休みにどんな参考書を使うかも大切ですが、自分に合ったレベルの参考書を、焦らず、しかし着実に進めていくことが一番重要だと私は感じています。
今回ご紹介した参考書は、私自身や合格した友人たちが実際に使ってきたものです。
受験全体で使うべき参考書については、以前の記事でも紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
詳しくはYouTubeチャンネル「教育嬢TV」でもお話ししています。ぜひご覧ください🙇♀️
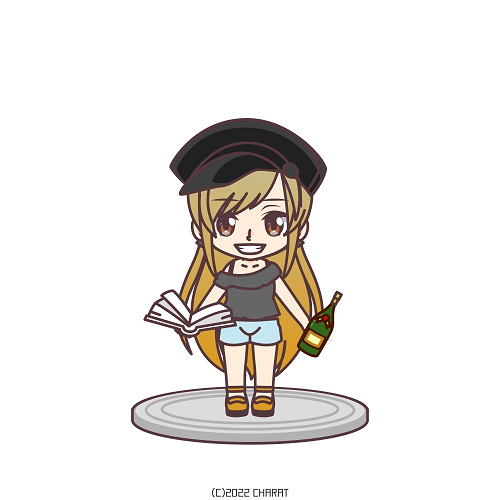
受験メンタルトレーナー/チャイルドコーチングアドバイザー
地方公立中高一貫校から特色入試(AO入試)で京都大学薬学部に現役合格
中高時代は運動部の活動・個人研究・学業を両立
大学在学中は大手予備校の塾講師として勤務し、受験指導やメンタルサポートの経験を積む
卒業後は母校でアドバイザーとして高校生の指導、地元個人塾でカリキュラム作成、オンラインを中心とした受験コンサルティングも展開中