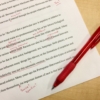高校3年生の11月にやるべきこと|共通テスト目前の最後の山場を乗り切る5つのポイント
11月がスタートしましたね。
いよいよ受験本番が目前に迫ってきました。共通テストまであと2か月、緊張や焦りを感じている人も多いのではないでしょうか。
夏から秋にかけて努力してきた成果が模試の結果や演習の精度に現れはじめ、志望校の合格が少しずつ現実的になってくる時期です。一方で、時間のなさに不安を感じたり、思うように点数が伸びないことで焦る人もいると思います。
そんな11月は、まさに「受験直前の山場」。ここでの過ごし方が、1月・2月の入試結果を大きく左右します。
今回は、高校3年生・浪人生が11月にやるべき5つのポイントを紹介します。
「あと2か月」をどう使うか、一緒に考えていきましょう。
共通テストと二次試験の“バランス”を見直す
10月までは「二次中心+共通テストは授業でカバー」だった人も、11月に入るとそのバランスを再調整する必要があります。
共通テストの形式に慣れることは大切ですが、ここで共通テスト対策ばかりに偏ってしまうと、二次試験で使う記述力や論理的思考力が鈍ってしまいます。
この時期の理想的なバランスは例えば、
平日:共通テスト6割+二次試験4割
休日:二次試験演習中心(共通テスト演習を1~2科目)
のように、共通テストの実戦感覚を養いつつ、二次力を維持するスタイルです。
また、二次試験の過去問はまだすべてを解き切る必要はありません。
苦手な科目や分野を優先して、“解ける問題を増やす”ことを目的に演習を進めましょう。
特に国公立志望者は、配点比率によってどちらを重視すべきかが変わります。
共通テストの比重が高い大学なら、11月中旬以降は共通テスト演習に重きを置くのがおすすめです。
模試を「本番」として活用する
11月は、ほとんどの受験生にとって冠模試の最終シーズン。
東大・京大・阪大などの大学別模試をはじめ、駿台や河合塾では最終実戦模試が行われます。
この時期の模試は「受けること」ではなく「本番のように挑むこと」が重要。
試験時間や昼休みの過ごし方、持ち物、集中のリズムなど、入試当日を想定してシミュレーションするつもりで受けてください。
そして、模試の後にやるべきは結果の数字だけを見ることではありません。
* 問題のどの部分で得点できなかったか
* 記述のミスがどんな傾向にあるか
* 本番で時間が足りなかった理由は何か
これらを丁寧に分析することが、本当の“模試の復習”です。
模試の点数が思うように伸びなくても落ち込む必要はありません。
むしろ「今の自分の弱点を見つけるための模試」だと捉えて、12月の最終仕上げに活かしましょう。
数字で見える目標設定をする(共通テストリサーチを意識)
「志望校に合格したい」という気持ちは当然ですが、今の時期に必要なのはもっと具体的な“数字の目標”です。
たとえば次のように設定してみましょう。
* 共通テスト英語:80分でリーディング85点、リスニング70点
* 数学ⅠA:60分で70点以上
* 二次数学:120分で3完+部分点2問
このように「何分で・何点取るか」を意識して演習を重ねると、実力の伸びが見えるようになります。
さらに、ここで意識しておきたいのが「共通テストリサーチに向けた目標点設定」です。
共通テスト後のボーダーライン分析では、各大学・学部ごとに「得点率○%でC判定」といった指標が出ますが、
11月の段階でそれを想定した“目標得点ライン”を先に決めておくことが重要です。
たとえば、
* 第一志望:得点率80%
* 安全校:得点率70%
* 共通テスト重視型の併願校:得点率85%
このように大学ごとに数字を置いておくと、模試の得点や演習の進捗が「どの大学レベルに届いているか」を可視化できます。
また、共通テストリサーチ(ボーダーライン判定)は年によって平均点の上下があるため、「理想ライン」と「最低ライン」の2つを設定しておくとより現実的です。
たとえば「英語80点/最低70点」「数学ⅠA 70点/最低60点」のように目標と許容範囲を分けることで焦りが減ります。
数字を意識して勉強すると、モチベーションが下がったときにも「今どの位置にいるのか」が明確になり、学習計画の修正も立てやすくなります。
時間を意識した実戦演習をする
11月以降の勉強では、「どれだけ解けるか」ではなく「どれだけ時間内に解けるか」が重要です。
ここまでの時期にインプットはある程度完了しているはず。
これからは、実際の試験時間を想定して“時間配分の練習”にシフトしましょう。
おすすめは次の2ステップです。
1. まずは時間を計って本番通りに演習する
→ 何分でどの大問を解けたかをメモし、ペースの感覚をつかむ。
2. 次は試験時間より10〜15分短く設定する
→ 「見直しの時間を確保できる状態」で解く習慣をつける。
この練習を繰り返すことで、入試当日の焦りが激減します。
また、共通テストのリーディングやリスニングは“時間との勝負”です。
問題文を読むスピードを上げるには、演習のたびに「読む→解く→答え合わせ」までを時間計測付きで行いましょう。
体調管理とメンタルケアを最優先に
最後に、どれだけ努力しても体調を崩してはすべてが台無しです。
11月は気温の寒暖差が大きく、インフルエンザや風邪が流行する時期。
勉強量が増えて睡眠時間が削られがちですが、夜更かしは免疫力を下げる原因にもなります。
体調管理で意識すべきポイントは次の3つ。
* 睡眠を削らない(最低6時間は確保)
* 3食をできるだけバランスよくとる(特に朝食)
* 週1日はリセット日を作る(軽い運動やリラックス時間)
また、模試の結果や周りの合格報告を聞いて落ち込む人もいると思います。
でも、11月の段階では「伸びる人はここから一気に伸びる」という時期でもあります。
焦りを力に変えて、今できることを1つずつ積み重ねましょう。
小さな達成をノートに書き留めて「今日はこれができた」と自分を褒めることも、メンタルを安定させるコツです。
まとめ|11月は「本番シミュレーション月間」
11月は、知識を詰め込む月ではなく、本番のためのシミュレーションを重ねる月です。
勉強の量よりも「質」と「再現性」にこだわりましょう。
* 共通テストと二次のバランスを最適化する
* 模試を本番と同じ意識で受ける
* 数字で目標を立てて成長を見える化する(共通テストリサーチを意識)
* 時間を計った実戦演習で“得点力”を磨く
* 体調とメンタルを整えて入試本番を迎える
どれも当たり前のようでいて、意外とできていないことばかりです。
11月をどう過ごすかで、12月以降の自信が決まります。
1日1日の積み重ねを大切に、受験までの残り時間を最大限に活かしていきましょう。
詳しくはYouTubeチャンネル「教育嬢TV」でもお話ししています。ぜひご覧ください🙇♀️

受験メンタルトレーナー/チャイルドコーチングアドバイザー/JAPAN MENSA会員
地方公立中高一貫校から特色入試(AO入試)で京都大学薬学部に現役合格
中高時代は運動部の活動・個人研究・学業を両立
大学在学中は大手予備校の塾講師として勤務し、受験指導やメンタルサポートの経験を積む
卒業後は母校でアドバイザーとして高校生の指導、地元個人塾でカリキュラム作成、オンラインを中心とした受験コンサルティングも展開中