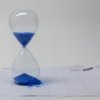総合型選抜受験生に向けて。この夏休みに考えてほしい面接想定問題集
夏休みに入り、そろそろ総合型選抜の準備を本格的に始める人も多いのではないでしょうか。学校や塾で提出書類の添削をしてもらったり、自分のこれまでの活動を振り返って志望理由書にまとめたりしているかもしれませんね。
その一方で、つい後回しになりがちなのが「面接対策」。書類に比べて見えにくく、「なんとかなるかな…」と感じてしまうかもしれませんが、実は面接こそが合否を左右する重要な場面だということも珍しくありません。
この記事では、面接でよく聞かれる質問をジャンル別にご紹介し、それぞれどのように向き合えばよいのかを解説していきます。最近特に問われやすい探究活動や国際経験に関するトピックにも注目しているので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
志望理由・入試方式に関する質問
この大学・学部を志望する理由は何ですか?
「なんとなく良さそう」「知名度が高いから」といった曖昧な答えでは、面接官の心に残りません。大切なのは、自分が何に興味を持ち、なぜその大学で学びたいのかという筋の通ったストーリーです。
たとえば、「環境問題に興味があり、高校の課題研究で地元の水質調査に取り組んだ経験から、大学でも環境保全を学びたい」といったように、自分の経験と大学の学びがつながっていることを具体的に語れると説得力が生まれます。
パンフレットやホームページをしっかり読み込んで、ゼミやカリキュラム、教授の研究分野などから「ここでしか学べないこと」を見つけ出しておくと、自信を持って語れるようになります。
なぜ一般選抜ではなく、総合型選抜を選んだのですか?
この質問では、「本当にこの方式を理解したうえで選んでいるか」が見られています。たとえば、「記述試験よりも面接や書類のほうが得意だから」という理由だけでは弱く、その方式を通して何を伝えたいのかを明確にする必要があります。
「これまでの活動や探究を通して、自分で考え、行動してきたことを評価してもらいたいと考えました」というように、自分と入試方式との相性に着目して答えられると好印象です。
自己理解・価値観に関する質問
あなたを一言で表すと?
「責任感がある」「柔軟性がある」など、自分を表す言葉は何でも構いませんが、大切なのはその言葉を裏づける具体的なエピソードを話すこと。
たとえば、「私は粘り強い性格です」と答えた場合、「部活動で引退前にケガをしてしまったけれど、リハビリを続けながらチームのサポート役を最後までやりきった」といったエピソードを添えると、言葉にリアリティが生まれます。
また、他人から言われた言葉を紹介するのも効果的です。「友人に『一緒にいると安心する』と言われた」といったように、他者から見た自分像を交えて話すと、客観性も加わります。
最近、嬉しかったことや悔しかったことはありますか?
出来事そのものよりも、そこから何を学んだのかに注目して答えましょう。「嬉しかったこと=褒められた」「悔しかったこと=失敗した」という表面的な話ではなく、その経験が自分にどんな気づきを与えたのかを掘り下げることが大切です。
たとえば、「チームで意見が対立したけれど、自分が間に立って調整し、最終的に良い結果につながった」という経験があるなら、「相手の立場に立って考えることの大切さを実感した」といった学びを含めると深みが出ます。
高校生活・日常の活動に関する質問
高校生活で最も力を入れたことは何ですか?
「何をやったか」よりも、「どんな思いで取り組んだか」「どんな工夫や努力をしたか」「その中で何を学んだか」といったプロセスや感情の動きに注目して語りましょう。
たとえば、「文化祭の実行委員としてクラス企画をまとめた」経験があるなら、「最初は意見がまとまらず苦労したが、全員のアイデアを聞く仕組みを作ったことで、徐々に一体感が生まれた」といったように、自分の役割と変化を含めると印象に残ります。
部活動やボランティア以外で頑張ったことはありますか?
この質問は、「見えにくい努力にスポットライトを当てるチャンス」です。家庭での役割、趣味での創作、地域での手伝い…何でも構いません。
たとえば、「家で小さいきょうだいの世話を毎日していた」「趣味の動画編集を通して発信力を高めた」といったことも、そこから何を感じ、どのように成長したかを語れば、その人らしさが伝わります。
社会・未来に関する質問
最近気になったニュースや社会課題はありますか?
この質問は、単に「ニュースを知っているか」を試されているわけではありません。面接官が見ているのは、そのテーマに対してどのように考え、自分の学びや将来とどうつなげているかという点です。だからこそ、将来の夢や志望学部とかけ離れたテーマを選ぶよりも、自分の関心分野と重なる話題を選び、深く掘り下げて話すことが大切になります。
たとえば医学部志望の人なら、「医療的ケア児への支援に関する報道を見て、医療の役割だけでなく、福祉や教育との連携の必要性を感じた」など、医療に関心をもったきっかけや、自分の志望理由にも通じる視点を交えて語ると、話に一貫性と説得力が生まれます。
「探究活動でもこのテーマに取り組んだ」「将来この分野に携わりたいと思っている」など、過去・現在・未来を一本の線で結ぶような構成にすることで、あなたの関心が一時的なものではなく、深く根づいたものだと伝わります。
将来の夢はなんですか?
この質問では、単に職業名を答えるのではなく、「なぜその夢を持ったのか」「どんなきっかけや経験があったのか」を含めて語ることが大切です。たとえまだ職業がはっきり決まっていなくても、「誰かの力になれる存在になりたい」「課題解決に挑みたい」など、自分なりの価値観や方向性を言葉にすることができれば十分です。
たとえば「教師になりたい」という夢がある場合、「小学生のときに出会った先生のように、生徒の可能性を信じて関わりたい」といった原体験や理想像を加えることで、話に深みが出ます。
また、今の学びや課題研究、ボランティアなどと夢がどうつながっているかを合わせて伝えると、将来像がより現実味を帯びて面接官の印象に残ります。
10年後、どんな自分でありたいですか?
この質問では、職業名を答えることが目的ではありません。たとえば、「医療職になりたい」だけでなく、「地域に根ざした医療を通じて、誰もが安心して暮らせる社会に貢献したい」というように、どんな価値を提供したいのかを明確に語ることが大切です。
「まだ具体的な職業は決まっていないけれど、誰かの人生の節目に寄り添えるような存在でありたい」といった心の軸が見える答えも素敵です。
探究・課題研究に関する質問
探究活動や課題研究について教えてください
テーマだけでなく、「なぜそのテーマにしたのか」「どういった疑問や仮説を持っていたか」「結果がどうだったか」など、思考と行動のプロセスを丁寧に語りましょう。
たとえば、「地域の空き家問題」をテーマにした場合、「身近な町で空き家が増えているのを見て、不安を感じたことがきっかけ」といった個人的な出発点があると、話に説得力が生まれます。
結果が思うように出なかった場合も、「仮説を修正しながら粘り強く調査を続けた」「思いがけない意見を聞いて視野が広がった」など、その経験から得た学びを語ることが大切です。
留学・国際活動に関する質問
留学で得たことや印象に残っていることはありますか?
語学力の向上や観光の楽しさだけではなく、異文化との出会いが自分にどんな影響を与えたかを語りましょう。
たとえば、「現地の学校で発表する機会があり、伝えたいことがうまく伝わらなかった悔しさから、自分の伝え方を見直すようになった」といった感情と行動の変化を含めて話すと、経験の深さが伝わります。
逆質問
最後に、何か質問はありますか?
ここで「ありません」と答えてしまうのはもったいないです。この質問は、自分がどれだけ大学について調べてきたか、そしてどれだけ強い思いを持っているかをアピールできる絶好のタイミングです。
「○○ゼミに関心があるのですが、学生同士で意見交換をする場はどのように設けられていますか?」など、学びに対する具体的な興味を示す質問を用意しておくと好印象です。
まとめ:この夏、自分自身を「言葉」にする時間にしよう
面接は、「うまく話すこと」よりも「心から伝えたいことを準備すること」が大切です。誰かと比べる必要はありません。大事なのは、自分の経験や価値観と、どれだけ誠実に向き合い、言葉にできるか。
この夏は、紙に書き出してみたり、家族や友人に話してみたりしながら、自分の中の「軸」をじっくり育ててみてください。
それが今後の面接で、あなたの言葉に力を与えてくれるはずです。
詳しくはYouTubeチャンネル「教育嬢TV」でもお話ししています。ぜひご覧ください🙇♀️

受験メンタルトレーナー/チャイルドコーチングアドバイザー/JAPAN MENSA会員
地方公立中高一貫校から特色入試(AO入試)で京都大学薬学部に現役合格
中高時代は運動部の活動・個人研究・学業を両立
大学在学中は大手予備校の塾講師として勤務し、受験指導やメンタルサポートの経験を積む
卒業後は母校でアドバイザーとして高校生の指導、地元個人塾でカリキュラム作成、オンラインを中心とした受験コンサルティングも展開中