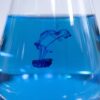京大薬学部卒がおすすめする数学の参考書
今回は参考書紹介シリーズ第2弾として数学の参考書を紹介していきます。
理系の学生は数Ⅲ数Cまで、文系の学生は数ⅡB数Cまでと習う範囲や分量にはかなり差がありますが、問題集に関しては数1A・2B・3も同じものを使っていたので、今回紹介する参考書は文系理系どちらの学生にもおすすめできるものです。
今回は私が使っていた数学の参考書の中でも皆さんに特におすすめしたいものを紹介したあと、さらに難易度が高い問題に挑戦したい皆さんに向けたおすすめ参考書も紹介していきます。
それでは基礎的なものから順にご紹介していきます。
4STEP
まずは、授業を受けた後、定期テスト対策として1番最初の演習に使っていたのが4ステップという参考書です。
私の学校では数1A・2Bが4ステップ、数3は4プロセスが配布されていたので、基礎演習にはこの問題集を使っていました。
他にも同じレベルの問題集としてプライムやスタンダードなどがありますが、皆さんも学校で配られている他の問題集があればそれを使って授業の復習をすると良いでしょう。
4STEPは持ち運びやすいサイズで解答編が別冊になっているので、ページをめくらなくても答え合わせができるという点で時短になって使いやすいです。
A問題、B問題、発展問題と分かれているので、A問題は授業が終わった日に解く、発展問題はテスト直前の確認のために解くというように使い分けることもできます。
私は数1の授業が始まった中学3年生から高校3年生まで授業に合わせて使っていました。
フォーカスゴールド
基礎がある程度固まった後に使っていたのがフォーカスゴールドです。
これも学校で配られたことがきっかけで使い始めたのですが、レベルとしては青チャートやレジェンドと同じぐらいで形式も似ています。
それらの中で学校指定の参考書がある人は、そちらに置き換えてみてください。
レベルの幅が広く問題数も多いため、志望校に合わせて問題を選ぶと良いでしょう。
単元ごとに受験に出る可能性の高い色々なパターンの問題が集められていて、例題と練習問題が交互に載っています。
例題で解き方を学んで、その解き方を忘れないうちに実際解いてみるという繰り返しも良いですし、各単元の後ろにある問題に挑戦してみるのも良いです。
問題量もかなり多いので、苦手単元のみ解いたり、星の数で解く問題を決めたり、章末問題だけ解くというように、それぞれの勉強のスタイルに合った使い方をするのがおすすめです。
私は応用問題に触れたかったので、テスト範囲として指定された問題に加えて星4・5の問題と章末問題に絞って演習していました。
高校3年生の夏あたりまでは4ステップや4プロセスで基礎を固めた後、すぐにフォーカスゴールドを解き進めていたのですが、それでは急にレベルが上がりすぎて、フォーカスゴールドの問題に苦戦していたのを覚えています。
この2冊では急にレベルが上がって難しいと感じる方は青チャートのレベル3の問題を使用したり、次に紹介する重要問題集を間に使ってみてください。
今から既に習った単元の復習もしようと考えている方は4ステップと青チャートレベルの2冊の使い分けがおすすめです。
青チャートで各単元をまんべんなく解き進める中で見つけた苦手単元は定期テストレベルの問題集に戻って復習すると良いでしょう。
重要問題集
私が重要問題集を使い始めたのは高校3年生の11月あたり、全ての単元を習い切ってからで、本番直前の総復習に使っていましたが、もう少し早い時期から取り組んでも良かったと思っています。
定期テストレベルと青チャートレベルの問題集の間に何か1冊演習問題集が欲しい人、例題と練習問題が同じページに載っているのが苦手で、問題と解答が分かれているタイプの問題集が好きな人におすすめの問題集です。
本番対策
各単元の基礎が固まった後、本番レベルにもう少し近づいて、文系理系の皆さんに共通して使える共通テスト対策の参考書も紹介しておきます。
私が学校から配布されて使っていたのはパワーマックスですが、学校で配られる同レベルのものがあればそれを使っても構いません。
共通テスト対策問題集を選ぶ時のポイントは大問数や設定時間が本番と全く同じ形式であること、過去問よりも少し難易度が高いことです。
共通テストと同じレベルの問題が単元ごとに集められている参考書もありますが、それでは本番に慣れるための練習にはなりません。
テスト形式で実際の共通テストと同じ時間設定のもので演習すると、時間配分の練習にもなります。
直前期は本番よりも制限時間を短く設定し、70分の試験であれば55分で目標点を越えられるようにすると、試験当日の緊張やトラブルにも打ち勝つことができるようになります。
パワーマックスは高校3年生の11月末以降、授業内で使っていました。
共通テストはまだ過去問も多くないので、予備校が作成した予想問題のパックを使うのもおすすめです。
駿台の青パックや河合塾、Z会のパックなどがありますが、Z会のパックはかなり難易度が高いので、余裕のある人はぜひ挑戦してみてください。
とにかく共通テスト対策は共通テストと同じ形式の問題を繰り返し、問題を解くスピードと正確性を上げることが重要です。
共通テストが近づいたらまた詳しい対策法についてもお話しします。
ここまでの問題集ができれば、後は志望校の赤本と共通テストの過去問を解くだけでも十分合格レベルに到達することができます。
難関大学対策
ここからはおまけとして難関大学を受験する人におすすめの参考書を2冊紹介します。
1冊目は大学への数学の新数学演習です。
毎月発売されている大学への数学とは違い、毎年9月に増刊号として出版される冊子で、2025年は7月に増刊号が発売されるようです。
全ての単元について難易度の高い問題が集められているので、数学がかなり得意な理系の学生や最難関大学の理系を目指すみなさんにおすすめの問題集です。
高校3年生になってから私もチャレンジし、全てを解ききることはできませんでしたが、先生にピックアップしてもらった問題をコツコツ解き進めたり、共通テスト前に記述数学の感覚を忘れないよう、数問ずつ解き進めるようにしていました。
新数学演習が理系最難関向け、新数学スタンダード演習が足固めとは言われていますが、新数学スタンダード演習でも難易度の高い問題が揃っているので、実力と志望校に合わせて挑戦してみてください。
2冊目はプラチカです。
私は複素数が苦手で問題演習が足りないように感じたので、演習量を増やすためにプラチカの数Ⅲを高校3年生の夏に買い足して演習していました。
プラチカ数Ⅲは特に難易度が高いので、本当に数学が得意で好きな人におすすめです。
フォーカスゴールドや青チャートレベルまで解ききって余裕があるという人は、プラチカに取り組むともう1段階レベルアップすることができるでしょう。
詳しくはYouTubeチャンネル「教育嬢TV」でもお話ししています。ぜひご覧ください🙇♀️

受験メンタルトレーナー/チャイルドコーチングアドバイザー/JAPAN MENSA会員
地方公立中高一貫校から特色入試(AO入試)で京都大学薬学部に現役合格
中高時代は運動部の活動・個人研究・学業を両立
大学在学中は大手予備校の塾講師として勤務し、受験指導やメンタルサポートの経験を積む
卒業後は母校でアドバイザーとして高校生の指導、地元個人塾でカリキュラム作成、オンラインを中心とした受験コンサルティングも展開中
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/27b4ac14.ed904d0a.27b4ac15.7f9535fd/?me_id=1213310&item_id=18260090&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2852%2F9784402272852.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/27b4ac14.ed904d0a.27b4ac15.7f9535fd/?me_id=1213310&item_id=21378469&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2314%2F9784410142314_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/27b4ac14.ed904d0a.27b4ac15.7f9535fd/?me_id=1213310&item_id=21235046&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7228%2F9784777227228_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)