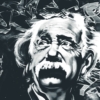夏休みの各科目勉強法〜苦手を克服するために
大学受験の合否を左右すると言われる夏休み。
一日一日の積み重ねが本番での“得点力”を作ります。
この時期、「どの科目をどう勉強すればいいかわからない」「苦手科目を放置してきたけど、さすがに不安…」という声を多く聞きます。
この記事では、各科目ごとに「これだけやれば、もう苦手とは言わせない」勉強法をギュッと詰め込みました。
全科目読まなくても大丈夫。あなたの“苦手”だけ、しっかり読んで、しっかり伸ばして、夏を終えたときに自信を持てるようにしていきましょう。
英語が苦手なあなたへ:文法こそ最大の武器
単語帳を頑張ってるのに点数が伸びない人は、まず文法に立ち返ってください。
英語の土台は、やはり文法です。
語順、時制、関係詞、仮定法…一通りの文法を理解することで、長文の構造がスッと見えるようになります。
【最低限やるべきこと】
・文法問題集を1冊やり切る
・間違えた問題は「なぜその選択肢が正解か」を自分の言葉で説明する
・長文読解は、1日1題の精読から始める(構文を全部確認しながら読む)
・文法知識がついたら、精読から徐々に速読に移行して感覚を育てる
・リスニング・音読は1日10分、“聞こえるようになる”より“構造が聞き取れる”を目指して
文法がわかるようになると、単語も文の中で覚えられるようになり、読むスピードも自然と上がってきます。
「読む」「聞く」「話す」「書く」すべての力の根っこを鍛える夏にしましょう。
国語が苦手なあなたへ:読み方に“視点”を持てば変わる
「現代文はセンス」と思っている人、ちょっと待ってください。
実は、読み方の“視点”さえ身につければ、国語はちゃんと点が取れるようになります。
【最低限やるべきこと】
現代文:問題集の解説を熟読し、「なぜこの選択肢が正しいのか/違うのか」を徹底分析
筆者の主張・対立関係・具体例にマーカーを入れる練習をする
古文:単語帳を1冊、毎日10語ずつ音読して覚える
古文文法は助動詞と敬語を優先。表で覚えて→本文で確認→演習で定着
漢文:句法(レ点・一二点・再読文字など)と頻出漢字の意味を暗記+音読
国語は一見得点の波が激しいように見えて、読み方が定まると一気に安定します。
特に古文・漢文は“型”さえ身につければ伸びるので、得点源にしやすいですよ。
数学が苦手なあなたへ:型を理解し、解法のストックを着実に積む
「問題集を解いてるのに模試では解けない…」
そんな人は、“公式や解き方を覚えるだけ”で終わっていませんか?
数学は、「どの問題に、どの解法を使うか」の判断ができるようになることがカギです。
つまり、ただ覚えるだけでなく、「使える解法のストック」を頭の中に整理していく必要があります。
【最低限やるべきこと】
・解いたら終わりではなく、“なぜこの解法なのか”を自分の言葉で説明してみる
・解法を整理するノートやアプリを作り、似た問題をまとめて管理
・解き直しを「間違えた問題だけ」ではなく、「自信がなかった問題」まで含めて行う
・手が止まったらすぐ解答を見ず、「似た解法はなかったか?」と自分のストックを振り返る練習をする
数学の実力は、理解×演習量×解法の引き出しの多さで決まります。
その中でも夏休みに特に意識してほしいのが、“引き出しをどう増やすか、どう整理するか”。
1つの単元でも「典型問題+そのバリエーション」が解けるようになれば、模試での得点は安定してきます。
この夏は、数学を「なんとなくやる」から「目的をもって積み上げる」学びへ、ステージを1つ上げていきましょう。
化学が苦手なあなたへ:有機化学を制す者が、化学を制す
化学は、「用語が多いし計算もあるし…」と敬遠されがちですが、理論・無機・有機・高分子という分野によっても特徴が大きく異なるもの。
まずは有機化学をマスターすれば、大きな武器になります。
【最低限やるべきこと】
・有機の基本(官能基・構造決定・反応経路)を1冊の問題集で固める
・自分で構造式を“描いて覚える”ことが理解への近道
・同じ反応がどうつながっているかを“ストーリー”として整理する
・資料集や図説を見ながら学習 → 視覚で覚えると定着しやすい
有機が完成すると、化学全体の安定感が一気に増します。
しかも、有機は“典型問題が多く、演習が得点に直結しやすい”という利点つき。
この夏、有機だけでもマスターできれば、化学は確実に得点源になります。
物理が苦手なあなたへ:図で理解すれば、公式は自然と使える
「公式が多すぎて覚えられない」「何を求めればいいのかわからない」
そんなふうに感じている人は、まず“図を描く”習慣をつけましょう。
物理は、「公式を覚える」よりも「現象をイメージする」ことの方がずっと大事です。
【最低限やるべきこと】
・問題を読んだら、必ず図を描く(力の向き・運動の変化・位置関係を視覚化)
・どの公式を使えばいいかではなく、「何を求めたいのか」から逆算する
・基礎問題集を繰り返し、「1問ごとに“なぜその式を使ったか”を説明できるように」
・苦手な分野(力学・電磁気など)は“最初の設定”の読み解き練習を重視
点が安定しない人ほど、式を機械的にあてはめがちですが、それだと応用には対応できません。
図+式の意味理解=物理の得点力です。
「式の裏にあるストーリー」が見えるようになると、物理は急にやさしくなりますよ。
生物が苦手なあなたへ:流れと因果を“物語”として覚える
「用語が多すぎて覚えきれない」「読んでも意味がわからない」
そんな人にこそ、生物は“流れ”で覚えることをおすすめします。
生物の内容は、バラバラに覚えようとするとつらいですが、ストーリー仕立てにすれば、驚くほど整理されます。
【最低限やるべきこと】
・「DNA → RNA → タンパク質」などの生命の基本サイクルを図で確認しながら暗記
・遺伝・生態系・代謝など、分野ごとに“順番”と“因果関係”をつかむことを意識
・教科書や資料集の図表を使って、目で見て覚える(図そのものを再現できるように)
・用語単独ではなく「○○は□□のために起きる」という形で説明できるようにする
記述問題にも対応できるようになるには、「なぜそうなるのか?」を説明できる力がカギになります。
知識がつながると、生物は“理解できる科目”に変わり、得点が安定してきます。
社会が苦手なあなたへ:暗記ではなく“線でつなげる”発想に
社会=暗記のイメージが強いかもしれませんが、覚えるだけでは本番で通用しません。
地理・歴史・公共すべてに共通して言えるのは、「関連づけて覚える」ことです。
【最低限やるべきこと】
地理:地図帳を開きながら、農業・工業・気候などテーマごとに場所とセットで覚える
日本史/世界史:年号より「流れ」。「この出来事→次の時代にどうつながったか?」を意識
公共:時事とセットで学ぶ。憲法・国会・経済・国際問題などはニュースアプリを併用
関連づけを意識して学習すると、知識が“引き出しやすく”なります。
「用語を見て、背景や意味を思い出せる」ようになれば、記述でもマークでも強くなれます。
おわりに:苦手は、伸びしろ
苦手科目を放置しない夏にできたら、それだけで他の受験生と大きな差がつきます。
完璧じゃなくていいんです。「足を引っ張らないレベル」に持っていくことが目標。
この夏の1日1日が、あなたの得点力をつくります。
どの科目にも、「これだけはやっておきたい」基礎が必ずあります。そこをしっかり固めて、夏明けの模試で“確かな手応え”を感じられるようにしていきましょう。
詳しくはYouTubeチャンネル「教育嬢TV」でもお話ししています。ぜひご覧ください🙇♀️

受験メンタルトレーナー/チャイルドコーチングアドバイザー/JAPAN MENSA会員
地方公立中高一貫校から特色入試(AO入試)で京都大学薬学部に現役合格
中高時代は運動部の活動・個人研究・学業を両立
大学在学中は大手予備校の塾講師として勤務し、受験指導やメンタルサポートの経験を積む
卒業後は母校でアドバイザーとして高校生の指導、地元個人塾でカリキュラム作成、オンラインを中心とした受験コンサルティングも展開中