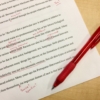今日から使える!受験に効くおすすめ暗記法10選〜あなたに合った覚え方で合格をつかもう〜
受験生なら誰もが通る“暗記の壁”。でも大丈夫。
記憶は「やり方」で劇的に変わります。たった一つのコツで、「覚えやすい!」「忘れにくい!」を実感できるかもしれません。
今回は、暗記が苦手だった私が試して効果のあった暗記法を10個、厳選してご紹介します。
勉強の効率を上げたい人、ぜひ最後までチェックしてみてください!
すでに実践している暗記法や、自分なりの工夫がある方は、ぜひコメントやSNSでシェアしてくださいね!
短期記憶を長期記憶に変えるために
短期記憶は一夜漬けなどで身につけた一時的な記憶です。
試験直前に焦って一夜漬けをし、テストまでは覚えていられたからといって満足している方もいるかもしれませんが、1日で覚えた記憶はすぐに忘れてしまいます。
受験までの長期的で応用可能な知識にするためにはさらに時間をかけ、理解しながら暗記をしていく必要があります。
理解をしていない暗記はただ言葉の羅列を覚えるだけなので、覚えるのも大変ですし、忘れやすくなってしまいます。
理解をして覚えながら反復をすることで、忘れにくい知識に変わっていきます。
これを前提に暗記法についてお話ししていきます。
赤シートで隠す
まずは王道、赤シートを使った暗記法です。参考書や単語帳には、赤字やオレンジ文字で記載された重要語句が多く、シートで隠して確認することを前提に設計されています。ただ眺めているだけではなく、「思い出す」ことに意味があります。
私が実践していた方法は、理科や社会の教科書に緑のペンで大切な語句やポイントに線を引き、赤シートで隠しながら読むというもの。最初は1周して内容をざっくり把握し、2周目からは隠しながら「ここ、何が書いてあったっけ?」と自分に問いかけるようにして読み直していました。5周、10周と繰り返すうちに、記憶が自然と定着していきます。
赤シートは、勉強を“受け身”から“能動的”に変える手助けをしてくれるツールなのです。
青ペンで書きなぐる
次にご紹介するのは、青いペンでひたすら書いて覚える方法です。裏紙やノートに覚えたい内容を何度も書くことで、視覚だけでなく、手の感覚を使って記憶を定着させることができます。
青色には集中力を高める効果があるとも言われており、私は青のボールペンを何本も使い切る勢いで勉強していました。特に英単語や社会の語句などは、頭の中だけで覚えたつもりでも、本番では意外と出てこないことがあります。ですが、青ペンで何度も書いてきた内容は、手の感覚とともに頭に残っていることが多く、試験中にスッと出てくる感覚がありました。
青ペンのインクが減っていくのを見ると、「今日も頑張ったな」と達成感も得られ、勉強のモチベーション維持にもつながります。
読みながら書く
音読は、暗記を定着させるためにとても有効です。視覚・聴覚・発話という複数の感覚を同時に使うことで、脳の複数の領域が活性化され、記憶に残りやすくなります。
特に英語や古文など、リズムや音のある科目では絶大な効果があります。私は英語の教科書を毎日音読していました。意味を考えながらフレーズごとに繰り返すうちに、文法構造や重要表現が自然と体に染み込んでいきました。
音読は雑念を排除するのにも役立ちます。黙読では気が散ってしまうという人には、特におすすめの方法です。
歩きながら覚える
座りっぱなしでの勉強に疲れたとき、気分転換も兼ねてノートを片手に歩きながら暗記してみてください。歩くというリズム運動によって、脳の血流が良くなり、記憶の定着が促されると言われています。
私は、試験直前の暗記や、単調な単語の確認などにこの方法を使っていました。声に出して歩きながら覚えると、テンポも良くなり、集中力も持続しやすくなります。自宅や塾の廊下など、周囲の迷惑にならない範囲でぜひ試してみてください。
よく行く場所に貼る
勉強時間以外にも知識に触れるチャンスはたくさんあります。たとえば、トイレのドアや洗面台、冷蔵庫など、日常的によく目にする場所に覚えたいことを貼っておくことで、無意識のうちに記憶が積み重なっていきます。
私は、トイレには化学の構造式、洗面所には英単語、リビングには数学の公式を貼っていました。実際、試験中に「あのとき冷蔵庫の横に貼ってあったあれだ!」と、場所の記憶とセットで思い出せたこともあります。
自分の生活空間を“第二の参考書”にするような感覚で、学びを日常に組み込んでみましょう。
寝る直前に覚える
睡眠中、脳はその日得た情報を整理・定着させています。そのため、寝る直前に覚えたことは記憶に残りやすいと言われています。
私は、就寝前5〜10分を「暗記タイム」と決めて、紙の単語帳やまとめノートを見返していました。そのあとスマホを見ずに眠るようにすると、翌朝、記憶がクリアな状態で残っていることが多かったです。
ただし、画面の光は睡眠の質を下げてしまうことがあるため、紙の媒体を使うのがポイントです。
テスト形式にする
「知っている」と「思い出せる」は別物です。自作テストを通して“引き出す力”を磨くことが、得点力アップに直結します。
私は間違えた問題をノートにまとめて“間違い直し帳”を作り、何度も解き直していました。家族に問題を出してもらう、友達とクイズ形式で出し合うなど、さまざまな角度から“出力”の練習を積むことで、知識がしっかりと脳に根付いていくのを感じました。
モニターより紙で覚える
スマホやタブレットでの学習は便利ですが、記憶の定着という観点では紙に軍配が上がります。紙のテキストやノートは、自分の手で書き込んだり、付箋を貼ったりといった操作ができるため、学びが“身体化”されやすいのです。
私は、英単語や社会の語句を電子アプリで覚えていたときよりも、紙の単語帳で反復した方が、模試や過去問での思い出しやすさが段違いでした。手間がかかるように見えて、実は近道になる方法です。
友だちと勉強する
誰かと一緒に勉強することは、記憶の定着に大きく貢献します。友達と問題を出し合ったり、疑問点を一緒に考えたりすることで、新たな気づきや視点を得ることができ、理解が深まります。
私は、休み時間に友人と5分だけ問題を出し合う時間を設けていました。「なぜそうなるのか」を説明する過程で、自分の知識がどこまで理解できているのかを再確認できるのも、この方法の良いところです。
逆授業で覚える
最後に紹介するのは「逆授業」暗記法。これは、自分が先生になったつもりで人に教える前提で勉強するという方法です。
私は、歴史の出来事を覚えるときに「これを中学生に教えるとしたら、どんな順番で話すか」を考えながらまとめノートを作っていました。人に説明するには内容を深く理解していないとできません。逆授業は、その“理解の深さ”を自分自身で引き出すための最強ツールです。
ここまで10種類の暗記法をご紹介してきました。自分に合いそうな方法は見つかりましたか?
暗記は、「自分に合ったやり方を見つけること」からすでに勝負が始まっています。まずは一つでも構いません。試してみて、「これなら続けられそう」と思える方法を継続してみてください。そして、慣れてきたら複数の方法を組み合わせていくことで、さらに記憶の質が高まっていきます。
詳しくはYouTubeチャンネル「教育嬢TV」でもお話ししています。ぜひご覧ください🙇♀️

受験メンタルトレーナー/チャイルドコーチングアドバイザー/JAPAN MENSA会員
地方公立中高一貫校から特色入試(AO入試)で京都大学薬学部に現役合格
中高時代は運動部の活動・個人研究・学業を両立
大学在学中は大手予備校の塾講師として勤務し、受験指導やメンタルサポートの経験を積む
卒業後は母校でアドバイザーとして高校生の指導、地元個人塾でカリキュラム作成、オンラインを中心とした受験コンサルティングも展開中