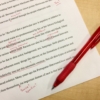大学受験合格に必要なこと【後編】―効率の良い長時間勉強と自分に合った勉強法―
同じ学校、同じクラスで学び、同じように勉強していたはずなのに、第一志望に合格できる人とできない人が出てくる。
なぜ、同じような環境にいながら結果が分かれてしまうのか。
その違いは、勉強量や塾に通っているかどうかといった表面的な要素だけでは語りきれません。
前編では、受験に必要な「戦略」と「目標設定」についてお話ししました。
明確なゴールと計画を持つことが、志望校合格への第一歩です。
では、その目標に向かって日々の勉強をどう積み重ねていけばいいのでしょうか?
後編では、受験合格に向けて必要な「効率の良い長時間勉強の方法」と「自分に合った勉強法の見つけ方」について解説していきます。
ただ頑張るだけでは、合格は難しい
勉強時間が長い=合格できる。
そんな風に考えていませんか?
もちろん、一定の勉強時間は必要ですが、ただ長時間机に向かっているだけで合格できるほど、大学受験は甘くありません。
たとえば、漫然と問題を解いたり、手を動かしているだけでは、記憶には定着せず、点数にもつながりにくいのです。
大切なのは、「目的を持って」「集中して」「継続的に」学ぶこと。
効率の良い勉強を、できるだけ長時間続ける力こそが、最終的に合格をつかむ決め手になります。
効率よく長時間勉強を続けるための5つのポイント
勉強の「意味」と「目的」をはっきりさせる
ただ「今日も勉強しないと。」と思うのではなく、
「この単元を理解すれば、次の模試で◯点アップする」
「この問題集を終わらせれば、弱点の◯◯が克服できる」
というように、勉強の目的を明確にすることがモチベーションの維持に繋がります。
科目をローテーションして、集中を持続
1日中英語だけ、あるいは数学だけという勉強法は、集中力が続きにくく、効率も下がりがちです。
脳の働きを活かすために、科目を時間帯ごとに切り替えることで、リフレッシュしながら継続的に勉強が可能になります。
脳はずっと同じペースでは働きません。
集中力のピークを活かすために、朝の時間は暗記科目、夜は復習や演習系など、時間帯に応じて科目を切り替える工夫も効果的です。
休憩をうまく取り入れる
人の集中力が続くのは50分程度が限界とも言われています。
長時間机に向かうためには、適切な休憩と科目の切り替えが不可欠です。
「25分集中+5分休憩」を基本とするポモドーロ・テクニックなどを使えば、効率よく勉強し続けられます。
短い休憩中にストレッチをしたり、軽く散歩するだけでも脳はリセットされ、次の集中力が高まります。
勉強の記録をつけて見える化
自分が「どれだけ勉強したか」「どの科目を頑張ったか」を記録していくと、進捗が目に見えてわかり、達成感があります。
また、計画と実行のギャップも明確になるので、改善すべきポイントが見えてきて、軌道修正もしやすくなります。
私も高校2年生から受験まで、毎日勉強の計画と記録をノートにつけていました。
隙間時間の活用も積み重ねに
通学時間や休み時間、食事後のちょっとした時間。短い時間でも、英単語や漢字の復習、リスニングなどに使うことで、1日あたり20〜30分以上の追加学習が可能です。
1日20分でも、1ヶ月では10時間以上、今から入試までにも100時間以上の差がつくことになります。
「自分に合った勉強」を見つけるには?
勉強法に“正解”はありません。
人によって集中できる時間帯、理解しやすい方法、得意・不得意科目は異なるため、ある人には効果があった方法でも、自分には合わないこともあります。
大事なのは、自分自身の性格や今の学力に合ったやり方を見つけることです。
ここからは今の皆さんの勉強が自分に合っているか、確認してみましょう。
基礎と応用のバランスは合っている?
基礎が固まっていないのに応用問題に取り組んでしまったり、逆に、応用力を伸ばすべきタイミングなのに基礎だけを繰り返していたり…。
このような実力と演習問題レベルのミスマッチは、学習効率を著しく下げてしまいます。
自分の現在地を正確に把握し、段階的にレベルアップしていくことが重要です。
他人の勉強法をそのまま真似していない?
成績の良い友達や先輩の勉強法をマネしたくなる気持ちはよくわかります。
ですが、「その人に合っている方法=自分に合う」とは限りません。
成功するためには他人の成功体験を、自分に合うように調整する必要があります。
成功している人の方法を参考にし、自分の集中力や性格、得意・不得意をもとに、最適な学習スタイルを見つけましょう。
得意科目・苦手科目の戦略を立てる
得意科目はどんどん伸ばし、苦手科目は「捨てる」のではなく「最低限の得点を取る」戦略が必要です。
特に共通テストなどは、全科目得点する必要があるため、バランス良く対策を行う必要があります。
自分だけの“ルール”を作る
人によって朝が得意か、夜が得意か、どの時間にどんな勉強をするのが最適かも違います。
たとえば…
・1日のはじめに計画を立てる
・昼食後は数学の演習
・寝る前に必ず英単語を50個確認
こうしたルーティンが習慣化すると、自然と勉強のリズムが身につきます。
まとめ:大学受験は「戦略 × 習慣 × 自分軸」
ここまで、前後編を通して、大学受験に必要な要素についてお話してきました。
前編では「受験戦略」と「目標設定」、後編では「効率的な長時間勉強」と「自分に合った勉強法」
合格するためには、「とにかくやる」だけでは足りません。
自分の目標に合わせた戦略を立て、それに沿った計画を実行し、自分らしい方法で日々積み重ねていくことが大切です。
効率の良い勉強法、自分に合った方法、そして戦略的な学習計画。
これらを武器にすれば、現在の成績や環境にかかわらず、確実に志望校合格に近づくことができます。
毎日の小さな積み重ねが、大きな結果を生み出します。
「今日やるべきこと」を明確にして、一歩一歩、確実に前に進んでいきましょう。
詳しくはYouTubeチャンネル「教育嬢TV」でもお話ししています。ぜひご覧ください🙇♀️

受験メンタルトレーナー/チャイルドコーチングアドバイザー/JAPAN MENSA会員
地方公立中高一貫校から特色入試(AO入試)で京都大学薬学部に現役合格
中高時代は運動部の活動・個人研究・学業を両立
大学在学中は大手予備校の塾講師として勤務し、受験指導やメンタルサポートの経験を積む
卒業後は母校でアドバイザーとして高校生の指導、地元個人塾でカリキュラム作成、オンラインを中心とした受験コンサルティングも展開中