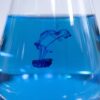模試を100%活用する4つのポイント
今回のテーマは模擬試験です。
進研模試や全統模試、駿台模試など、学校単位で受験するところもあるので、すでに何度か受験したことがある方も多いのではないでしょうか。
模試の緊張感が本番の試験の練習や成績を伸ばすきっかけにもなります。
それはそうなのですが、模試もただ受けるだけでは成績も伸びませんし、受験にも生かせません。
受験の仕方を少し変えるだけで、1度の模試を成績に繋げることができるようになります。
ということで、今回は、受験に向けて模試を最大限有効活用するために、模試前日から返却日までにやるべきことを時系列でお話ししていきます。
知識の総復習
まずは模試に向けた準備に関するお話で、試験前日と模試当日の朝、受験科目全体の知識確認をして試験に臨むことが大切です。
模試は、学校の定期テストとは違い、今まで習ったこと全てが出題範囲になっています。
出題範囲が広すぎることもあり、当日の朝は何をしたら良いかわからないまま、なんとなく試験時間を迎えてしまう人も多いのではないでしょうか?
定期テストの時は覚えていたはずなのに、少し時間が経って簡単な公式もうっかり忘れてしまった…という経験もあるかもしれません。
出題範囲全ての問題を前日の夜や当日の朝、解き直すのは難しいので、簡単に確認できる知識だけを対象にして、直前に見ておくのがおすすめです。
そうすることでもったいない失点をなくすことができます。
例えば、理系科目であれば、公式や自分が間違えやすいポイント、英語であれば少し複雑な文法や自分が苦手な単語・文法だけでも見直すのが良いでしょう。
ふだんの勉強中から、各科目、模試の直前にやることを決めておいたり、最終チェック専用のノートを作っておいたりすることで、試験直前の限られた時間にやるべきことに迷わなくなります。
科目によっても、人によっても、今の実力を出し切る直前準備の仕方というのは違うので、模試を利用していくつかの方法を試しながら、自分にあった復習の仕方を見つけておくことが大切です。
今のうちに試験前の勉強法が確立できていれば、受験前日にも同じことをすれば、最大限の点数が取れるという安心感もあります。
私が実践していた具体的なお話をすると、英語は先生が作ってくれた文法のまとめプリント全体に目を通し、システム英単語プレミアムの語源編で、接頭語と接尾語だけをチェック。
数学は、問題集で間違えた問題があった時に間違えた理由をまとめていたので、自分が間違いやすいポイントと公式の見直し、さらに、模試当日の朝には頭を起こすために、記述問題を2、3問解いてから試験を受けるようにしていました。
私も試験前のこのルーティンができてからは、緊張することなく試験を受けられるようになりました。
時間配分の練習
実際、模試を受ける際に1番重視してほしいのは時間配分の練習です。
試験時間の使い方を考えずに、前から問題を解いていくと、大問を残したまま試験時間がおわってしまったり、解けそうな問題に手をつけられないまま終わってしまったりするということもあるかもしれません。
特に時間設定が厳しい共通テスト模試では、時間が足りなくて焦ることもあるのではないでしょうか。
時間配分の練習をするためにはまず、試験時間が始まったら、問題文を読み始める前に問題用紙を最後までめくって全体を見ること。
そして、大問1つに何分ぐらいかけられるのかイメージしてから解き始めると、後半に焦ることも無くなります。
解けない問題があったら、考えすぎずに飛ばし、解ける問題だけ最後まで解き切ってから、余った時間に戻ってじっくり考えるようにするということも大切です。
難しい問題を考え過ぎて時間を取られてしまうと、その後にある簡単な問題も手をつけられなかったり、解けそうで解けない問題に時間をかけられずにあと一歩で正解にたどり着かなかったりします。
そうなってしまうぐらいなら、難しい問題を諦めて、解けそうな問題に時間をかける方が、結果的に良い点数を取ることができます。
そして、どの科目でも、見直しの時間は必要です。
最後10分は見直しの時間にすると決めたら、解き終わっていない問題があっても全体の見直しをするようにすると、マークミスや解答欄ずれなどの、勿体ない失点がなくなります。
落ち着いて問題を解ききるためには、問題を解く順番をあらかじめ決めておくということもポイントです。
私は最初から順番に解くのが好きでしたが、例えば国語に関しては時間のかからない古典から解いてその後で現代文を解くという人もいました。
時間配分や問題を解く順番は、模試を使って練習することで、特別意識することなく、できるようになっていきます。
自己採点
模試が終わった後には、何ができていて、何ができていなかったかの分析をするために、当日中に自己採点をすることも大切です。
正確な自己採点をするためにも、問題用紙に自分が選んだ解答を書き込んでおき、模試から帰ったら、すぐに自己採点できるようにしておくと良いでしょう。
模試結果が返ってくるまで待てば良いと、解答の書き込みをしない人もいるようですが、入試本番は共通テスト自己採点結果から出願校を最終決定することになります。
共通テストというのは、マークがずれていて大失点することもありますし、共通テスト数点の差が2次試験のボーダーラインや足切りラインに影響するので、マークミスが命取りになることもあります。
特に、試験の緊張感がある環境では、普段しないようなマークミスをしてしまうこともあるので、マーク模試を受ける際には、マークと採点のずれが全くなくなるよう、意識して練習しておくことが大切です。
記述模試に関しては、自分の解答を忘れてしまうこともあるので、当日のうちに自己採点しておくと良いでしょう。
記述には微妙な違いがあるので、自己採点の段階で正確な点数をつけることは難しいかもしれませんが、加点対象や減点対象となる文章がどのようなものなのかは確認するようにしてください。
単元別成績の把握
実際に模試の結果が返ってきたら、自己採点と正確な点数を見比べながら、自己採点と実際の点数にずれがないかの確認、内容の復習、データの分析をします。
最後に、模試の成績が返ってきた際の数字やデータ分析のポイントをお話しします。
点数や順位、偏差値、判定も大切なデータですが、そのデータだけを見て一喜一憂する必要はありません。
1番見るべきなのは単元別の成績です。
各科目の単元別の平均点と、自分の成績を見比べることで、どの単元が身についていないかがわかります。
科目ごとの点数や偏差値から得意不得意を判断し、対策を立てることも大切ですが、さらに細かい単元別の得意不得意を把握することがより大切で、それにより、効率的に点数アップを目指すことができます。
また、このタイミングで、試験直前の勉強法が自分に合っていたのかの判断を全体的な成績からできると良いでしょう。
模試をただ受け身で受験するか、知識確認・時間配分・自己採点の練習をするかどうかで、身につくことの量が大きく変わります。
次に受験する模試からは、ぜひこれらのポイントを意識してみてください。
詳しくはYouTubeチャンネル「教育嬢TV」でもお話ししています。ぜひご覧ください🙇♀️
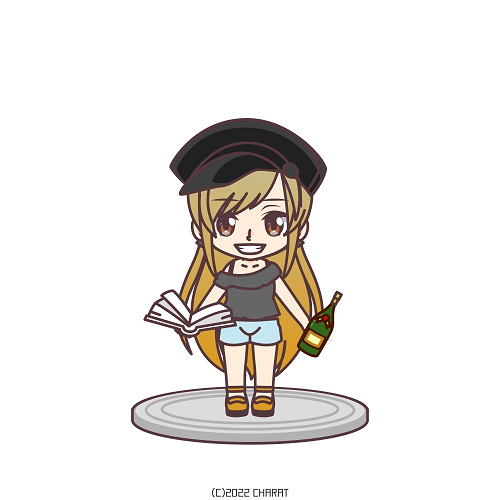
受験メンタルトレーナー/チャイルドコーチングアドバイザー
地方公立中高一貫校から特色入試(AO入試)で京都大学薬学部に現役合格
中高時代は運動部の活動・個人研究・学業を両立
大学在学中は大手予備校の塾講師として勤務し、受験指導やメンタルサポートの経験を積む
卒業後は母校でアドバイザーとして高校生の指導、地元個人塾でカリキュラム作成、オンラインを中心とした受験コンサルティングも展開中