地方公立高校から京大薬学部に合格!超効率的勉強法大公開
みなさんは自分の勉強スタイルを聞かれたらなんと答えますか?
私は高校3年間、超効率重視の勉強を続けていました。
地方公立高校に通い、高校3年生まで運動部を続けていた私は学習環境がすごく良かった訳でも勉強漬けの毎日だった訳でもありません。
そんな私が京都大学薬学部に合格するまで、短い勉強時間で超効率的に確実な点数をとるために実践していた勉強法についてお話ししていきます。
朝勉強
まず、勉強をするのは必ず朝。4時に起きて6時まで勉強をしてから1日の活動を開始するようにしていました。
私は朝練習も放課後練習もある部活に所属していて、1日4、5時間は部活をしていたので、部活が終わってからの時間は眠くなってしまって勉強に集中できない日もありました。
疲れて寝てしまって勉強ができない日がないようにするためにも、1番疲れの溜まっていない朝、起きてすぐにまずは勉強をするという習慣に切り替えました。ご飯を食べる前の空腹状態の方が集中できるとも言われていますし、友だちが誰も起きていない時間なので、SNSや連絡も気にならないというのも朝の方が勉強に集中しやすいポイントです。
毎日全科目に触れる
効率的に全科目の勉強をするためにも考えるべきことは科目バランスです。
1週間、1ヶ月の中で科目バランスを取れるように計画を立てている人も多いのではないでしょうか。
ですが、今日は数学を勉強する日、今日は英語の日のように決めていると、最近やったことを思い出しながら計画を立てなくてはいけません。
私は丁寧に計画を立てる時間ももったいないように感じていたので、1日の中で全科目に少しずつ触れるようにしていました。毎日全科目少しずつ触れると決めていれば、毎日やることが同じなので、改めて考えなくても自然と科目バランスがとれることになります。やるべき問題集や課題だけを決めてページ数や分量は決めないようにしておくと、その日のやる気や進み具合によって調整できるのでおすすめです。
演習系の科目に飽きたら暗記系の科目を挟むなど、時間のない時期や受験直前は特に、勉強の息抜きにも勉強をするようにしていました。
予習型か復習型か
予習授業復習という流れが推奨されていますが、全科目それぞれに時間をかけなくてはいけないわけではありません。
科目によって最適な方法を組み合わせると良いでしょう。
例えば私は予習をせずに数学の授業を聞くと途中で理解が追いつかなくなってしまうことが多かったので、予習をメインに勉強を進め分からない部分だけ授業中に理解する、暗記事項の多い理科や社会科目は授業を聞いてその日のうちにノートをまとめ直しながら知識を定着させるというようにしていました。
みなさんの得意不得意によっても最適な勉強サイクルは変わってくるので、各科目の勉強法を考え、実践してみてください。
分からない問題に時間をかけない
問題演習をしている中でわからない問題が出てきた時、みなさんはどうしていますか?
時間をかけて、何通りも解き方を考えてみたり、とりあえず飛ばして時間のある時に戻って解き直したり、感覚的にも差が出る部分です。私は問題演習をする際も限られた時間の中でできるだけ多くの問題に触れられるように、わからない問題には時間をかけないようにしていました。
時間をかけて解答を絞り出すという練習は確かに必要ですし、入試までの間にはその練習時間も確保する必要があります。ですが、部活をしている間は時間に余裕もなく、わからない問題にはどれだけ時間をかけてもできるようにはならないと考えていたので、分からない問題があったらすぐにじっくり解答解説を読みながら理解して、次は解けるようにするということを繰り返していました。
これは暗記系の科目でも同じで、時間をかけてまとめノートを作るよりも問題集を繰り返し解く中で覚えていくようにすると、周りの知識と絡めながら覚えることができます。
問題演習をする際はできるようになった問題は繰り返さずに、間違えた問題だけを解くというのも時間短縮につながるポイントです。
教えてもらう
1問1問に時間をかけすぎないという部分で、分からないことがあれば誰かに聞くということも重要です。
分からない問題に、多くの時間をかけて分かった気がするレベルで満足してしまったり、時間がないせいにしてそのまま放置してしまうと、その積み重ねで後から取り返せないほど苦手が増えてしまいます。
私は解説を読んでも理解できなさそうな問題には付箋を貼るなど印をつけておいて、塾や学校の先生にまとめて聞くようにしていました。
知識がない状態でいくら考えてもわからないので、知識のある人に分かりやすく教えてもらって理解する方が断然効率的です。そして、誰にいつ教えてもらったという情景と一緒に記憶されるのでテストの時も思い出しやすくなります。
自分で考える力も必要だと言われていますが、受験に関してはやるべきことも莫大な量なので、問題集を解いてわからない問題は解説を丁寧に読み込んで、納得できない部分に関しては人に聞くというサイクルにすることで演習できる問題の量が増えます。
この時に解答をさらっと読んだり人に聞いてわかったつもりになってしまうと、全く知識がつかないということになってしまうので、完璧に理解できるまで諦めないというのは必須条件です。
暗記法
最後に、受験勉強をするにあたって暗記は避けて通れないものです。
大学受験に関しては教科書以上の内容は出ることがないと言われていたので、理科や社会科目は教科書を端から端まで読み込んでいました。
テスト前には教科書を読みながら、覚えるべき部分に赤シートで隠す用の緑のペンで線を引き、緑ペンで線を引いた部分を赤シートで隠しながら読む、ということを完璧に覚えるまで何周も繰り返していました。
覚えていなかった部分に印をつけてそこだけ繰り返し見直せば時間もかかりません。
私は頭の中で思い出すだけでなく、紙に青ペンで書きなぐることも同時にしていました。暗記法は目で見る、手で書く、声に出すと言われていますが、目で見て考えて声に出しながら実際に書くというように全部同時に進めるのが効率的です。
軽い運動をしながらの暗記は効率も良いといわれているので、歩きながら唱えるという方法も実践していました。
これは特に眠くなった時、勉強に飽きた時、テスト直前に実践していた方法です。リフレッシュにもなりますし、頭に詰め込むという意味では歩きながら唱えるという方法がお気に入りでした。
詳しくはYouTubeチャンネル「教育嬢TV」でもお話ししています。ぜひご覧下さい🙇♀️
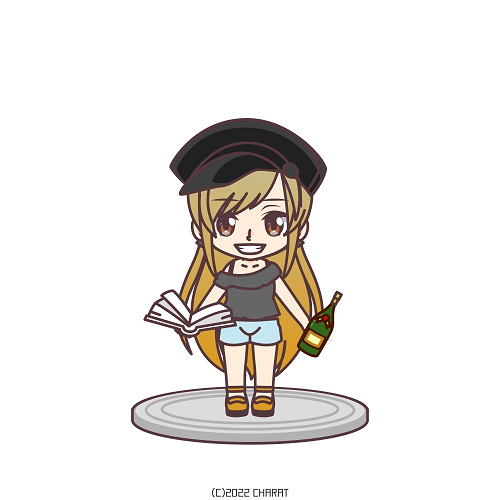
受験メンタルトレーナー/チャイルドコーチングアドバイザー
地方公立中高一貫校から特色入試現役合格で京都大学薬学部に進学。
中高時代は運動部の活動と学業、個人研究を両立。
大学生時代に事業立ち上げ準備の一環として大手予備校で塾講師として勤務。京都祇園のキャバクラに約2年間勤務し月間売上450万円を達成。
その後、地元仙台でキャバクラ勤務をし、月間売上500万円を達成。同時に母校でアドバイザーとして高校生の指導を行っている。











