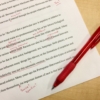高校3年生の9月、今やるべきこと
夏の暑さも少しずつ落ち着き、空気が秋らしさを帯びてきましたね。
受験に向けた“ラストスパート”シーズンの幕開けです。
高校3年生のみなさんにとって、この時期は夏休み明けの新しいスタート。模試や入試本番に向けて、気持ちを一段階引き締めるタイミングです。
夏までは高卒生と同じ模試で力の差を感じることがあった人も、ここからは同じ土俵で勝負できる手応えが出てくる頃。さらに、運動部を引退した生徒たちが驚くほど成績を伸ばしてくるのもこの時期です。部活組のエネルギーが勉強に全力で注がれることで、学年全体の雰囲気も一層熱くなります。
そして、本番に向けた模試ラッシュが本格的にスタート。ここからの数ヶ月で「何を」「どれだけ」やれるかが、志望校合格を左右する大きな分かれ道になります。
入試から逆算して考える
この時期、多くの受験生が「何を優先すべきか」で悩みます。
共通テスト対策を本格的に始めたい。でも、2次試験対策も手を抜けない。夏に使っていた問題集もまだ完璧ではない…。
そんな迷いが出やすいのは、入試本番までの距離感や期間が、現実的に見えてくるからです。だからこそ今は「入試から逆算」して行動計画を立てることが大切です。
逆算思考とは、単に「本番から日数を数える」だけではありません。
これは、志望校合格までの道のりを“設計図”のように描き、その図面通りに進んでいく方法です。
まずはゴール地点を明確にすることから始めます。
「〇〇大学△△学部に合格する」という最終目標を定めたら、その大学の試験日と配点、出題傾向を調べましょう。そこから「いつまでにどのレベルに到達していなければならないか」を逆算します。
例えば、1月中旬の共通テストまで残り4ヶ月。
共通テストを本格的に対策する時期を12月と決めるなら、9月〜11月は二次試験や私大の過去問演習に比重を置く期間です。
さらに細分化して、「10月末までに数学ⅠA・ⅡBの問題集2冊を完全に仕上げる」「11月は英作文と国語記述の添削を週2回行う」など、月単位・週単位の目標に落とし込みます。
このように配点や日程から逆算すると、「今やるべきこと」がはっきり見えてきます。結果的に、過去問がまだ手付かずでも不安に振り回されることがなくなります。
志望校や入試方式によって配点や日程は異なります。
例えば東大のように共通テスト110点、2次試験440点という配点なら、2次重視で動くべきです。一方、山形大学医学部のように共通テスト950点、個別試験700点と共通テスト比率が高い場合は、共通対策を早めに厚くする必要があります。
勉強だけじゃない!逆算思考は生活面にも
逆算思考は勉強計画だけでなく、入試当日までの生活準備にも有効です。
受験会場近くのホテルや交通手段の確保、出願準備、受験票の写真撮影、予防接種のスケジュールまで、すべて入試日から逆算して管理できます。こうした生活面の準備を早めに終えることで、直前期に100%勉強に集中できます。
「気づいたら予約がいっぱいだった…」という事態を避けられますし、先に予定を押さえておくことで気持ちにも余裕が生まれます。
夏の総仕上げと“次のステージ”への移行
9月時点でまだ夏休みの問題集が終わっていない場合は、まずそれを仕上げることが第一歩です。基礎が固まった科目から、少しずつ応用レベルの演習や過去問に入っていきましょう。
私の場合、この時期からZ会の添削課題を利用して京大の過去問を解き始めました。1ヶ月で1年分程度のペースで、ゆっくりですが、十分な基礎力を持った状態で過去問を見ると、自分の弱点がより明確になります。
また、私立大学も含めて出題傾向を確認するのもおすすめです。過去問は直前期に取っておくべき分量も考え、やみくもに早く手を付けすぎないことが大切です。
共通テスト本試験と追試験を含めれば10回分、2次試験は7年分程度で、直前期にやり切れる分量です。
定期テストとの向き合い方
受験期の定期テストは、多くの人が「時間を取られる存在」と感じます。
ですが、考え方を少し変えるだけで、定期テストは入試対策に直結する“無料の演習機会”に変わります。理想は、普段から定期テスト範囲の基礎を固め、確認テスト感覚で挑める状態にしておくことです。
まず大切なのは、普段から定期テスト範囲を前倒しで潰しておくことです。
授業が進むたびに、その範囲の基礎問題はその日のうちに解いてしまう。こうすれば、テスト直前にゼロから覚える必要がなくなり、直前は受験レベルの応用問題や過去問演習に時間を使えます。
また、定期テストの勉強方法を受験仕様にアップデートすることもポイントです。
たとえば理科や社会では、教科書暗記だけで終わらせず、同じ単元の入試問題も1〜2問解いておく。英語の本文暗唱や現代文の精読も、共通テストや二次試験の形式に近づけて練習する。これにより、学校の評価も取りつつ、入試対策も同時並行できます。
もちろん、すべての科目を完璧に仕上げる必要はありません。
入試で使わない科目は基礎確認に留め、重点科目に時間を回すのも戦略です。先生への礼儀は大切ですが、自分の合格を第一に考える時期であることも忘れないでください。
理想は、定期テストを「自分の受験勉強の進捗確認イベント」に変えることです。
「範囲の基礎は完璧、応用もある程度できる」状態で受けられると、テストのたびに自分の実力が伸びていることを実感できます。
目標の再設定
ここからは目標設定もアップデートしましょう。
学校内順位や模試偏差値だけでなく、志望校の合格ボーダーから逆算して「科目ごとの必要得点」を明確にするのです。
そして、その目標は3段階で設定します。
・理想目標点数(最高の状態で挑んだときに目指す点)
・現実的な目標点数(合格を狙うための得点)
・最低限確保したい点数(これを取れば合格可能性が残るライン)
勉強中は常に理想目標を意識し、当日もし緊張しても最低ラインは超えられるように計画すると、心に余裕を持って本番を迎えられます。
まとめ——9月からの一歩が合否を分ける
9月は、夏で築いた土台をさらに成長させる重要な時期です。
入試から逆算した計画、効率的な演習、そして心の余裕をつくる生活準備。この3つを意識して行動すれば、秋以降の伸びは確実に加速します。
「まだ間に合う」ではなく、「ここからが本番」。
そんな気持ちで、この秋を走り抜けましょう。
そして受験の日、最高の自分で挑めるように、今日から一歩を踏み出してください。
詳しくはYouTubeチャンネル「教育嬢TV」でもお話ししています。ぜひご覧ください🙇♀️

受験メンタルトレーナー/チャイルドコーチングアドバイザー/JAPAN MENSA会員
地方公立中高一貫校から特色入試(AO入試)で京都大学薬学部に現役合格
中高時代は運動部の活動・個人研究・学業を両立
大学在学中は大手予備校の塾講師として勤務し、受験指導やメンタルサポートの経験を積む
卒業後は母校でアドバイザーとして高校生の指導、地元個人塾でカリキュラム作成、オンラインを中心とした受験コンサルティングも展開中