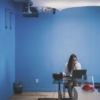京大薬学部卒が2年間継続!毎日の短期計画の立て方
今回は期間別の計画の立て方の中でも、毎日の短期計画についてお話していきます。
受験合格というゴールから逆算し、努力を着実に積み上げるためにも期間を分けた計画が大切であるというお話をしてきました。
前回までに受験までの長期計画、テストや模試までの中期計画の立て方についてはお話ししています。
今までに決めた計画をさらに細分化して毎日の短期計画を立てます。
今日やるべきことを考えてから1日の活動を開始するだけで、その日にこなすことができる仕事量が変わってきます。受験を控えた高校生だけでなく、運動部のトレーニング予定でや社会に出てからのタスク管理にも役立つことなので、ぜひ実践してみてください。
・バランスをとる
・ページ数を決めない
・毎日似たような計画にする
・見えるところに貼る
1日の中でバランスをとる
まず、今までの計画の立て方シリーズの記事で、計画を立てる目的の1つとしてバランスをとることがあるというお話をしてきました。
受験までという長い期間の中でバランスよく勉強をしようと思っても、気づいたら好きな科目や楽な勉強に偏ってしまっているということもあるのではないでしょうか。
私も元々は計画を立てるのが苦手で偏った勉強になっていましたが、毎日満遍なく色々な科目に触れるという勉強を毎日続けるようにしたことで、自然とバランスを取ることができるようになりました。
私は毎日の計画を立てるときに、昨日の計画や先週の計画を見直しながらバランスを考えるというのは時間がもったいないと思っていたので、時間短縮のためにも1日の中でバランスが取れるような計画にしていました。
そして、その日の中で取り組む順番は気分や空き時間次第で変えるようにしたことで、飽きずに勉強を続けることができました。
もちろんその日に取り組む科目を決めて1つのことに集中して勉強するというのもひとつのやり方ですし、集中力アップのためにはその方が効果的かもしれません。
ですが、例えば英単語の暗記や社会科目の暗記のように、科目によっては無理に長時間勉強しても定着しないというようなものもあるので、毎日少しずつ触れるという勉強法がおすすめです。
科目のバランスだけでなく、暗記と記述問題などのバランスも良くすると、飽きずに効率よく勉強を続けることができるようになります。
ページ数を決めない
計画を立てる際にはページ数や問題数までしっかり決めておいた方が良い計画だと思っていませんか?
私のような計画を立てるのが苦手な人・計画通りに勉強進めるのが苦手な人というのは、ページ数まで細かく決めようと思うと無理な計画になってしまったり、逆に余裕のありすぎる計画になってしまうこともあります。
計画はうまく立てられていても、問題集によっては難しい問題が続いて思っていたよりも時間がかかってしまうということもあるのではないでしょうか?
予定通りに勉強が進まないと計画が狂ってモチベーションも下がってしまうということになります。
余裕を持った計画にするためにも、ページ数を丁寧に決めすぎないように計画を立てていました。
どのテキストを何ページという計画ではなく、触れる科目やテキストだけを決め、問題の難易度やその日の勉強時間に合わせて柔軟に変更できるようにしておくと長続きします。
時間が足りなくなってしまった場合には、それぞれのテキストの分量で調節して、計画したすべての科目やテキストに少しでも取り組めるようにすると良いでしょう。
勉強のルーティンを決める
毎日似たような計画にするということも意識して短期計画を立てるようにしていました。
これは1つ目のポイントでお話ししたバランスの良い計画にするというポイントと被る部分も多いですが、1日の中で科目バランスの取れた計画をたてれば、その計画に沿った勉強を毎日続けることによって、自然とテストや受験までの間に科目や問題形式のバランスをとることができます。
バランスが取れる上に計画を立てる時間が短縮できるというのも毎日同じような計画を繰り返すべき大きな理由です。
加えて、もう一つ大きな理由があります。
それは勉強の細かい部分まで習慣化できるということです。
朝起きる時間やご飯を食べる時間、勉強を始める時間は決まっていた方が健康的で習慣化もしやすいと言われています。
それはさらに細かい勉強でも同じことです。
計画通りの勉強量をこなすことに慣れてくると勉強をする時間帯も決まり、その習慣が身につきます。朝起きてすぐ、通学時間、休み時間、自習でしっかり勉強時間を確保できるタイミング、寝る直前といった勉強時間にそれぞれ何をするかを決めておくことでだらけることなく勉強をスタートすることができます。
例えば私は朝起きてすぐは作業系の勉強と数学の記述問題を解く、通学中には英単語を覚える、寝る直前に暗記科目のテキストを読むといったように毎日の習慣を決めていました。
見えるところに貼る
立てた計画は1日中見やすいところに貼っておくということも大切です。
丁寧に計画を立てても鞄の奥底にしまってあって、見ることがなく、頭の中で思い出しながら勉強をしていると、最後に確認した時にやり残しが見つかるということもあります。
毎朝、付箋やメモ帳にその日の計画を書き出して、勉強机や筆箱など見えるところに貼っておくことで、常に計画を意識して勉強ができるようになります。
計画を箇条書きにしてチェックをつけながら進めていけば、進捗も一目で分かり、各科目や各テキストにかけられる時間を考えながら勉強に取り組むこともできるようになるのでおすすめです。
私は毎朝付箋に計画を箇条書きで書き、チェックをつけながら勉強を進めて、その日のうちに振り返りもするようにしていました。
・科目や問題形式のバランスをとる
・ページ数を決めずに科目やテキストで計画を立てる
・毎日似たような計画にして習慣化する
・付箋などに書いて見えるところに貼る
詳しくはYoutubeチャンネル「教育嬢TV」でもお話ししています。ぜひご覧ください🙇♀️
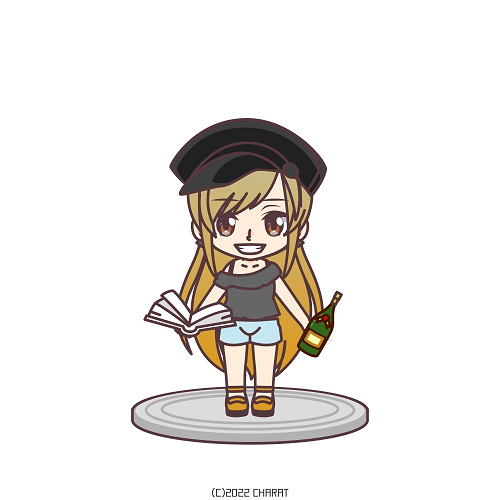
受験メンタルトレーナー/チャイルドコーチングアドバイザー
地方公立中高一貫校から特色入試現役合格で京都大学薬学部に進学。
中高時代は運動部の活動と学業、個人研究を両立。
大学生時代に事業立ち上げ準備の一環として大手予備校で塾講師として勤務。京都祇園のキャバクラに約2年間勤務し月間売上450万円を達成。
その後、地元仙台でキャバクラ勤務をし、月間売上500万円を達成。同時に母校でアドバイザーとして高校生の指導を行っている。