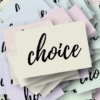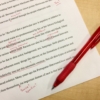共通テスト社会攻略法|まだ間に合う!3ヶ月で得点を伸ばす5つの戦略
10月に入り、いよいよ共通テスト対策が本格化してきましたね。
授業が終わり、自習時間が増えたという高校も多いのではないでしょうか。
特に共通テスト1日目の朝一番に受験する「社会」は、得点のスタートダッシュを決める重要な科目です。
理系の人にとっては苦手になりやすい一方で、社会は努力が点数に直結しやすい科目でもあります。
つまり、今からでもまだ十分に間に合うということです。
この記事では、共通テスト社会科目の勉強を効率よく進めるための5つの攻略ポイントを紹介します。
さらに後半では、日本史・世界史・地理・公共(倫理・政経)の分野別の対策法もまとめています。
どの科目にも共通する考え方なので、ぜひ最後までチェックしてください。
秋の共通テスト社会対策のポイント
過去問演習に入る前に河合塾共通テスト総合問題集など共通テスト対策の問題集を使用して、問題形式に慣れつつ、知識を固めることがおすすめです。
この時期の共通テスト対策のポイントは
・過去問を解きすぎない
・学校配布・共通テスト対策問題集中心の演習
・分からない知識はその都度固める
・間違えた問題だけをひたすら繰り返す
・分野別の“得点アップのコツ”を押さえる
という5つのことです。1つずつ詳しくお話ししていきます。
過去問を早く解きすぎない
共通テストまで3ヶ月あるこの時期、つい「過去問をやらなきゃ」と焦る人も多いですが、実はまだ早いです。
過去問を今のうちから解きすぎると、本番直前に解く新しい問題がなくなってしまうという落とし穴があります。
過去問は「最終調整」や「本番演習」として使うのがベスト。
特に12月以降は模試も減り、本番形式で力試しをしたい時期なので、今はあえて温存しておきましょう。
地理選択の人は特に注意が必要です。
地理は毎年データや統計が変化するため、古い過去問を使うと現在の傾向とズレてしまうこともあります。
12月以降に最新版の共通テスト総合問題集などを使って対策するのがおすすめです。
学校配布・共通テスト対策問題集中心の演習
この時期に最も効率がいいのは、学校配布の問題集や共通テスト用の演習書を徹底的に使うことです。
これらの教材は共通テストの出題傾向を踏まえて作られており、基礎力の定着に最適です。
例えば、河合塾の「共通テスト総合問題集」やZ会の「共通テスト実戦模試」シリーズなどは、形式や時間感覚をつかむ練習にもなります。
すでに一度やった範囲も、数週間経てば忘れていることが多いので、今のうちに総復習として解き直しておくと効果的です。
この段階では「スピードより精度」。
1問1問の選択肢を丁寧に検討し、「なぜその選択肢が間違いなのか」まで考える癖をつけましょう。
曖昧な知識はその都度固める
この秋以降は、1問ごとに「もう戻らないつもり」で解きましょう。
つまり、解いた問題で出てきたわからない知識は、その場で調べて覚えるのが鉄則です。
「あとで復習しよう」と思っても、共通テスト直前には他の科目で手一杯になってしまうのが現実。
今からは“即修正型の勉強”に切り替えるのが大切です。
具体的には、次のような方法が効果的です。
・不安な内容には必ずマーカーや付箋で印をつける
・覚えた知識は付箋を外すことで「達成感」を可視化する
・夜の5分復習で「今日間違えた問題」を確認する
曖昧な知識が減るほど、得点の安定感が上がります。
地味ですが、共通テスト社会は「どれだけ穴を減らせるか」が勝負です。
間違えた問題だけを繰り返す
残り時間が少なくなると、「もう1周全部解きたい」と思う人が増えます。
しかし、できる問題を繰り返すのは時間のムダです。
今やるべきは「間違えた問題だけをひたすら潰す」こと。
ノートに“間違いリスト”を作るのもおすすめです。
1ページに「問題・正解・なぜ間違えたか」をまとめておくだけで、見直しが圧倒的に効率化します。
特に理系の受験生は、理科や数学の勉強で社会に時間を割きにくいもの。
それでも「1日20分だけ社会をやる」と決めて習慣化すれば、3ヶ月で60時間の積み上げになります。
全範囲を完璧にしようとせず、「確実に取れる問題を落とさない」戦略に切り替えましょう。
分野別の“得点アップのコツ”を押さえる
ここからは科目ごとの具体的な勉強法を紹介します。
社会は「分野ごとの特性」に合わせて勉強法を変えることで、短期間でも得点を伸ばせます。
日本史・世界史:知識を“つなげて”覚える
共通テストでは、単なる暗記ではなく「知識の関係性」が問われます。
年号や人物を覚えるだけでなく、流れ・因果関係・地域のつながりを意識して学びましょう。
例えば日本史なら、政治の変化と文化・経済の流れを一体で整理する。
世界史なら、ヨーロッパとアジアの動きがどう連動していたかを意識する。
資料集を読み込んで「なぜこの出来事が起こったのか」を説明できるようにすると、8〜9割が狙えます。
公共(倫理・政治経済):教科書を“完璧”に
倫理や政経は、教科書・学校配布問題集の内容がそのまま出ることも珍しくありません。
難問よりも、基本知識の正確さで勝負が決まります。
倫理では思想家とその主張のペアを整理し、曖昧な区別(アリストテレスとプラトンなど)を正確に。
政治経済では、ニュースに出てくる時事用語をプラスで押さえると得点力が一気に上がります。
間違えた問題は「なぜその選択肢が正しいと思ってしまったのか」を分析し、思考のクセを修正しましょう。
地理:知識より“資料読み取り力”を磨く
地理は「覚えた知識を使って考える」タイプの問題が中心。
つまり、資料の読み取り力を鍛えることが最重要です。
統計・グラフ・地図を見たときに、どの情報がヒントになっているかを探す癖をつけましょう。
「平均値」「比率」「緯度」など、どこに注目すべきかを考えるだけでも正答率が上がります。
また、地理は最新データが反映されやすいため、冬期講習や直前期に「最新年度版」の問題集で演習を重ねると安心です。
まとめ:社会は“最後まで伸びる科目”
共通テストの社会は、今からの努力が最も反映されやすい科目です。
知識が点数に直結し、努力量がそのまま伸びにつながります。
最後に、今日からできる3つの行動をまとめておきます。
・1日20分でもいいから社会を“習慣化”する
・問題を解いたら必ず「調べて覚える」までやる
・間違えノートをつくり、苦手分野だけ繰り返す
理系でも文系でも、社会は「全体の底上げを狙える科目」です。
今からでも十分間に合うので、1問1問を大切に積み上げていきましょう。
詳しくはYouTubeチャンネル「教育嬢TV」でもお話ししています。ぜひご覧ください🙇♀️

受験メンタルトレーナー/チャイルドコーチングアドバイザー/JAPAN MENSA会員
地方公立中高一貫校から特色入試(AO入試)で京都大学薬学部に現役合格
中高時代は運動部の活動・個人研究・学業を両立
大学在学中は大手予備校の塾講師として勤務し、受験指導やメンタルサポートの経験を積む
卒業後は母校でアドバイザーとして高校生の指導、地元個人塾でカリキュラム作成、オンラインを中心とした受験コンサルティングも展開中